今回は、1987年に駿台政経科発行の「政治・経済資料集」をとりあげさせていただきます。

さっそくですが、はじめに、から見ていきます。
<はじめに>

この資料集は、理論という(抽象)の世界と、現実という(具体)の生活を結びつけるための最低限度の切符です。この切符がなければ。現実と理論を結ぶ鉄道の汽車に乗れなくなってしまいます。
人間は抽象的な一種の真空状態の中で生きているのはなく、、ある具体的な時空間の連続体で生存しているのです。
つまり、1980年代後半の日本という時空間、実定法、経済構造・経済規模が毎日の生活を規定しています。
と、書かれています。

そして…しかし(切符)をどのように活用するのか、という点は、ひとりひとりの主体性にかかっています。
この(切符)で、実際、どこまで行けるかためしてみてください。
と結ばれています。
<目次>

<GNP>
改めてGNPの定義を上げておきます。
国民総生産(こくみんそうせいさん、Gross National Product、略称:GNP)とは、ある一定期間にある国民によって新しく生産された財(商品)やサービスの付加価値の総計。
対して、現在使われているGDPは…
GDP(国内総生産)とは、国内で一定期間の間に生産されたモノやサービスの付加価値の合計金額のことです。つまり、日本が儲けたお金ということになります。
その内訳は、日本の国内総生産の大半を占めているのが、日本で生活する人々が日常的に行う「消費」と国内にある企業が行う「投資」の合計金額である「民需」です。
民需に加えて、政府が使ったお金である「政府支出」と輸出額から輸入額を差し引いた「貿易収入」 を合計した金額がGDP(国内総生産)となります。
1980年代頃から「対外投資などを通じて海外での生産活動に貢献した報酬を含んでおり、本来の国の生産量を正確に計ることができない」という理由から、国内総生産という概念が用いられるようになってきた、ということです。
1982年のGDPは、108兆2500億円(対ドル100円計算)です。
2018年のGDPは、536兆円と約5倍になっています。

世界第2位のGNPという言葉が盛んに取り上げられ、右肩上がりの経済に、何も疑いを持っていなかった頃。政治や経済などのやもすれば難しく感じることは、政治家や経済の専門家に任せて置いて、僕たち市井の一般人は、真面目にコツコツと仕事をすれば、きっとテレビCM等にある、アメリカナイズされた豊かな暮らしを手に入れられると無条件に信じていたのだろうと思います。
しかし、今や「自己責任」が求められる時代にあって、経済も政治にも関心を払い、グローバルなのだから、世界のそれにも視線を及ばせないと暮らせないように気分になっているかもしれません。

<経済理論Ⅰ>
学校でたくさん学んだ名前が出てきます。

まずは、トーマス・マン。

そして、必ずある、アダム・スミス。
世界史の中で、時代背景と名前を記憶していたと思いますが、今は名前だけしかわからないようになったのは、テレビのクイズ番組ばかり見ているからに違いありません。軽薄になっていると知っていても、物知りだと賢く見られるから、やめられないのは、どうしたものでしょう。



マルクス、レーニンを学んでも、天気予報すら当てられない。
どんなに賢くても、たかが明日の天気がわからないって、三上寛の歌にニヤケテイタものが、今なら天気予報バッチリ、時間単位で予想され、洗濯物を干すかどうかも毎朝の天気を見ればわかるし、今週のお出かけ日も予め決めておけるようになったのは、ありがたいことでしょう。

最後に、ケインズ博士。
僕は、法学部でしたが、アドビン・トフラーと、ケインズの名前は、何度も聞いて、その度に図書館で読んでいたように思います。
今は、「AI」がすべてやってくれそうな気分なので、もう一度、図書館に行こうとは思いませんが、書斎にある本は、大事にしたいと思います。
<市場経済のメカニズム>

循環の仕組みが図になっています。
その循環がぐるぐる回って、速度がだんだんに早まれば、景気が上昇していくとは理解出来そうです。
が、しかし、人口増加がそれを下支えしていた事が、欠けているのかもしれません。
この本のこれまでにあった理論や、メカニズムは、人口が減少することを全く予想していなかったように思えて仕方ありません。
家族が増えれば、新しい家が必要になり、新しいクルマにも需要が出来ます。衣服も人口増に合わせてやっぱり必要になり、学校も増え、本や文房具だって要ります。
日本国内の人口減少と、一人一人に豊かな生活づくりに向けて「そう、それなら納得出来る!」と拍手をしてしまう経済理論はあるのでしょうか?




上の表には、付加価値税とあります。名前が変わって、消費税になり、3%が5%に、そして10%になっても、それほど生活が困窮しているように思えないのは、気のせいでしょうか?
テレビニュースなどでは、街角のインタにビューに「税金があがると生活に直結していて、とても苦しい」と応えるものが流されます。
それって、訊き方がそういうように誘導しているんじゃないの?と疑問…
そして、ネットでニュース報道へのコメントを見て、自分と同じ感想を持っている人を探しているように思います。
<現代政治の諸問題>




政党政治って、どうかのか?と、もう一度考えないといけないようです。(自己責任が問われそうだから…)
保守と革新ってもう言わない、ようですが、ちゃんと考えて、政党を選ばなくちゃいけませんね。
下記にありますが、投票率が70%ちかくあったものが、今や半分になりそうなのが、危機的なのかもしれません。


マスコミの報道に一喜一憂せず、正々堂々とまっすぐに生活する根拠を求めて、今の経済状況から近い未来を予想して、誰に投票するかを考え直す、きっかけの資料になっている本だと思います。
次回のブログもお楽しみください。


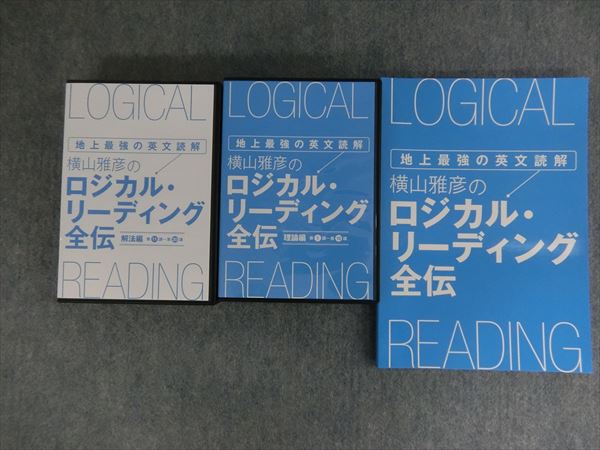
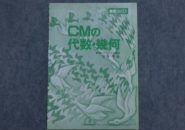

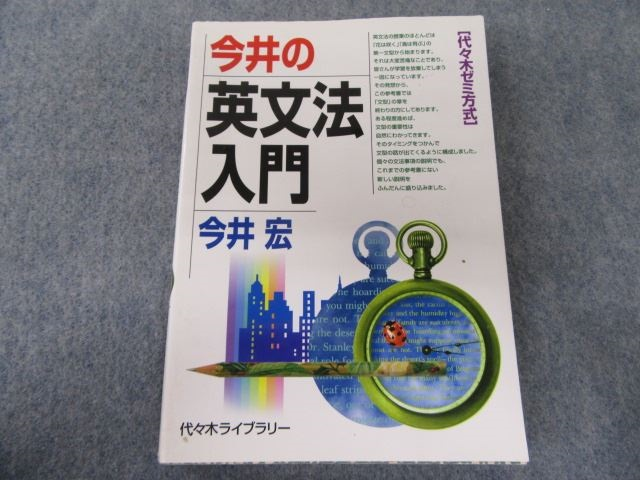

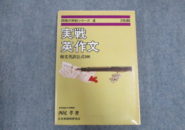
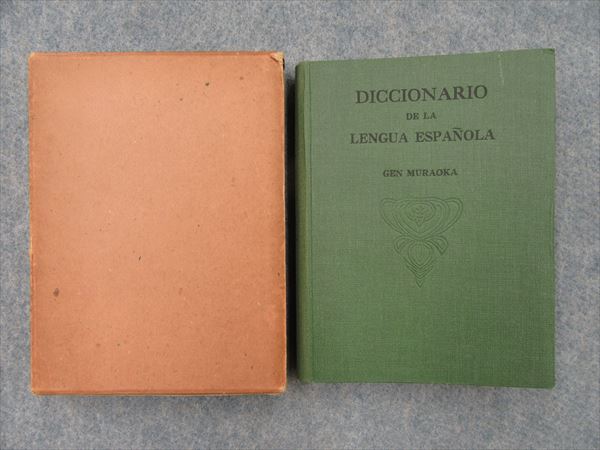

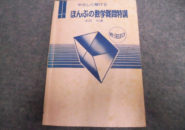
















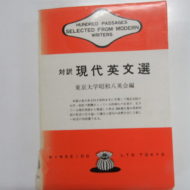

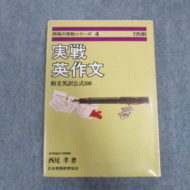

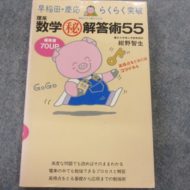


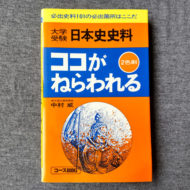



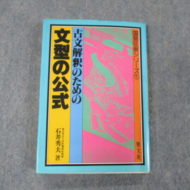



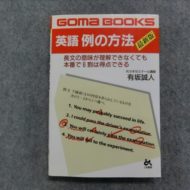
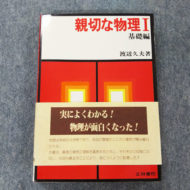



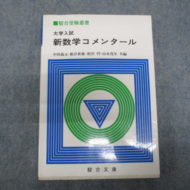

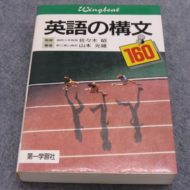
















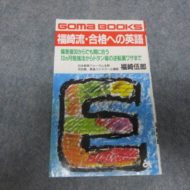
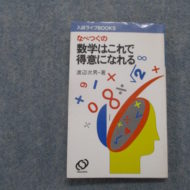








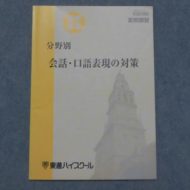
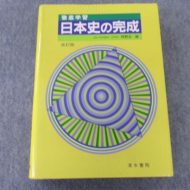










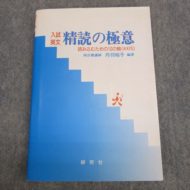






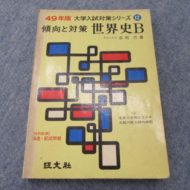

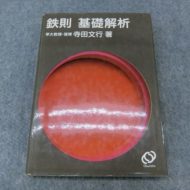




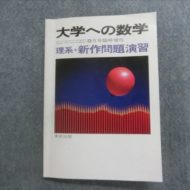

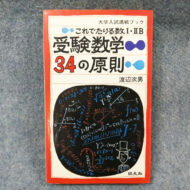





































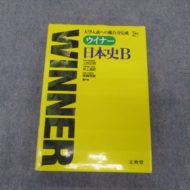







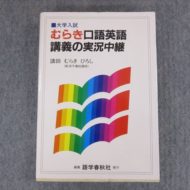




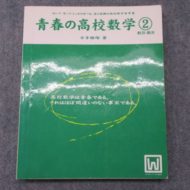




























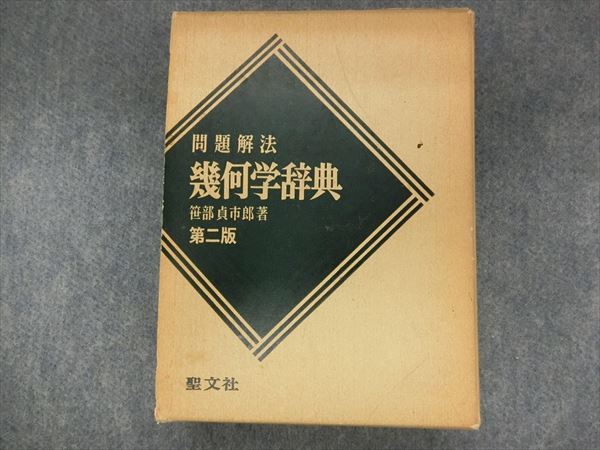









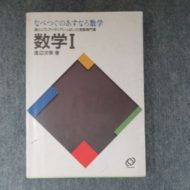
















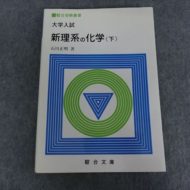




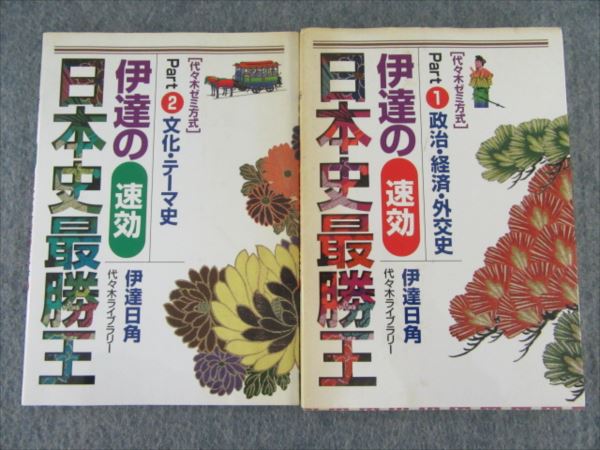

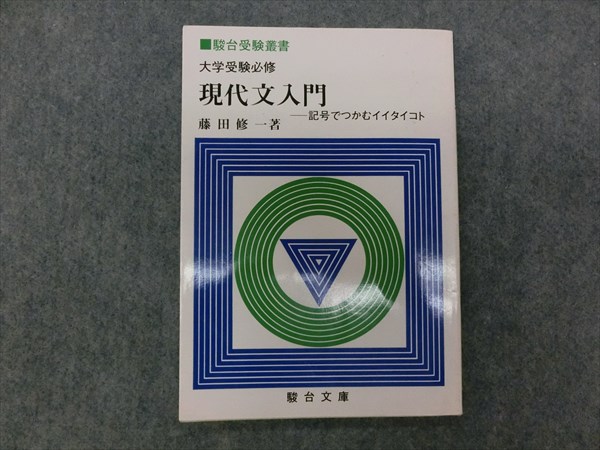
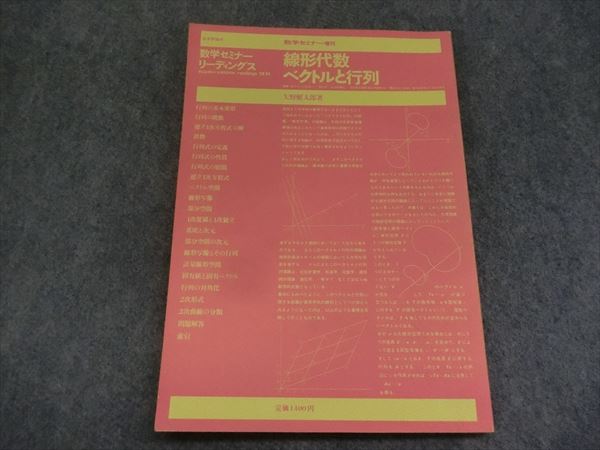
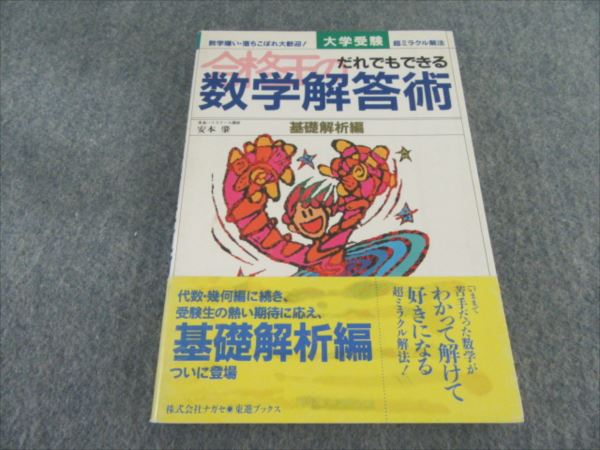


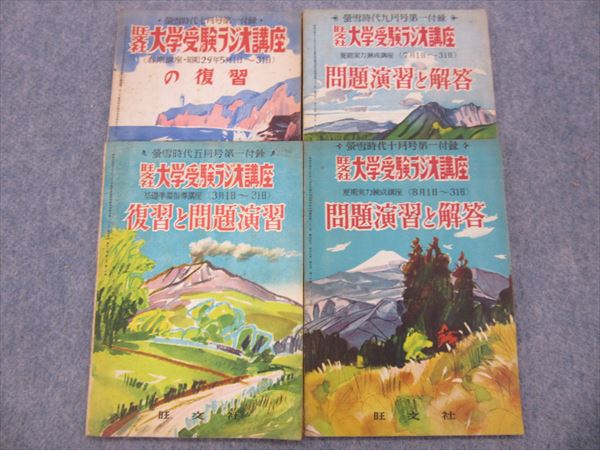

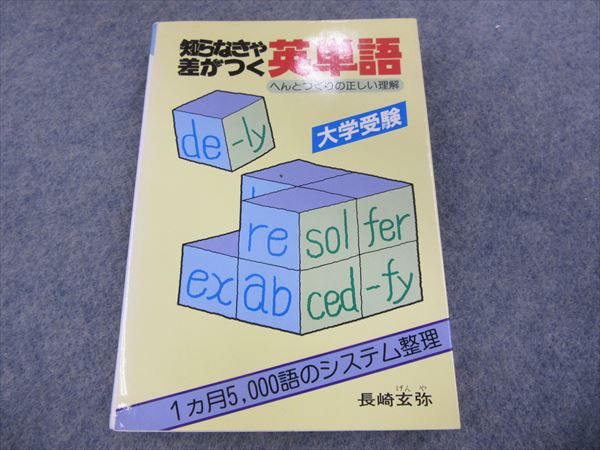





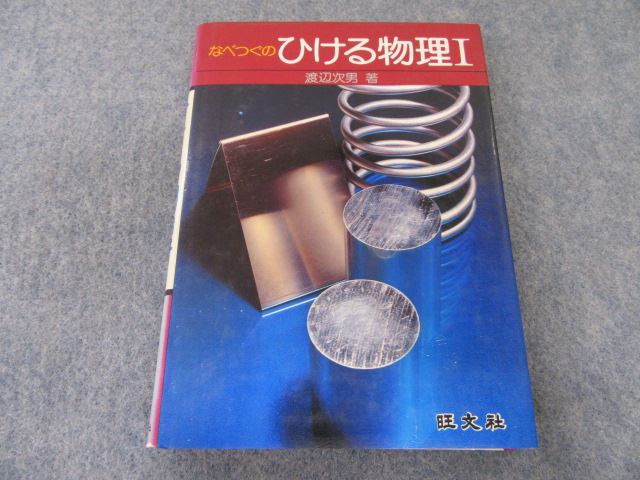
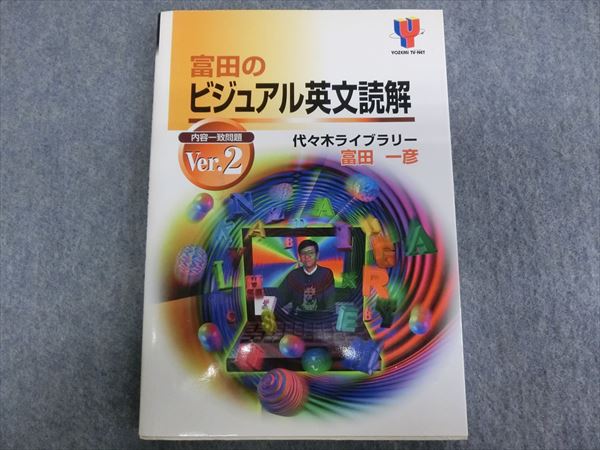
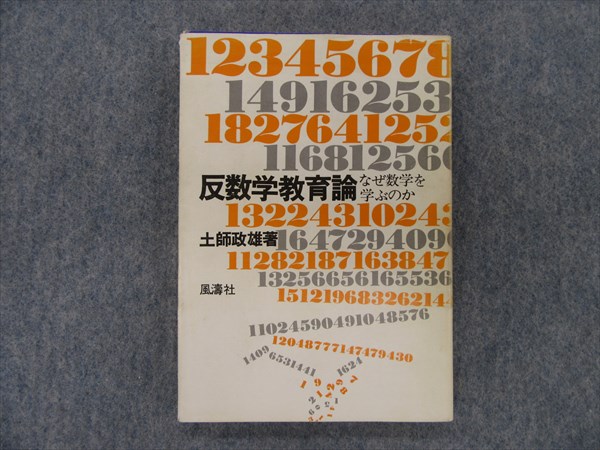
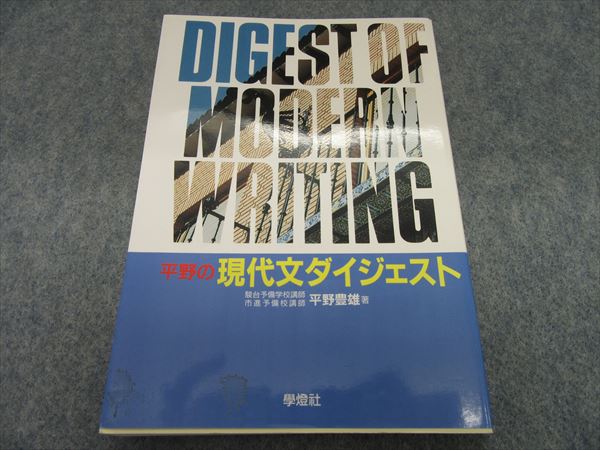
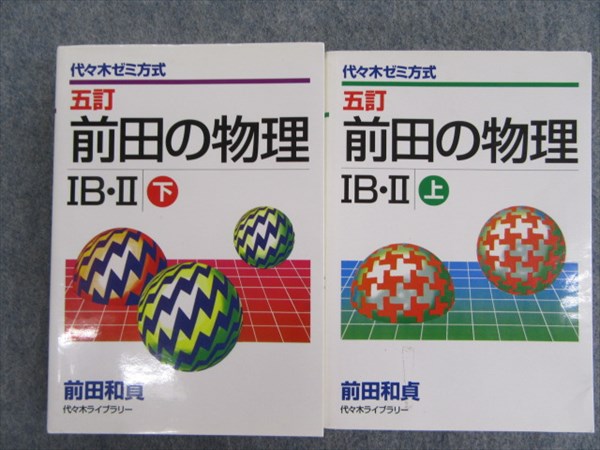
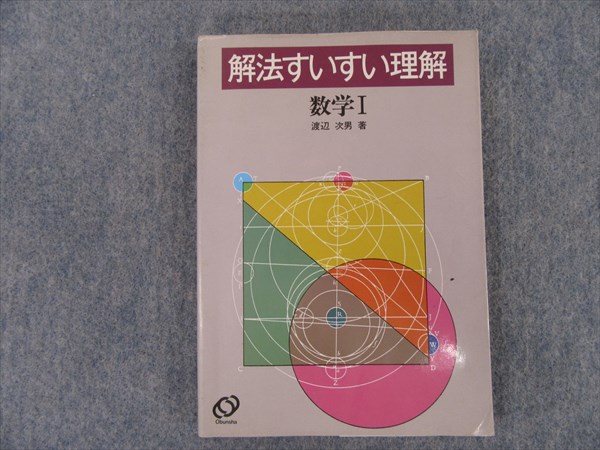
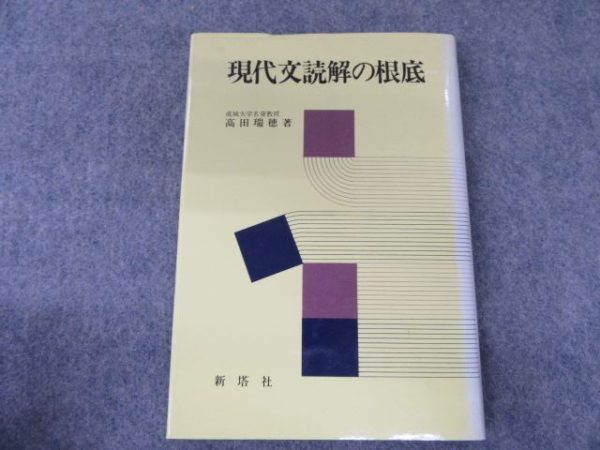
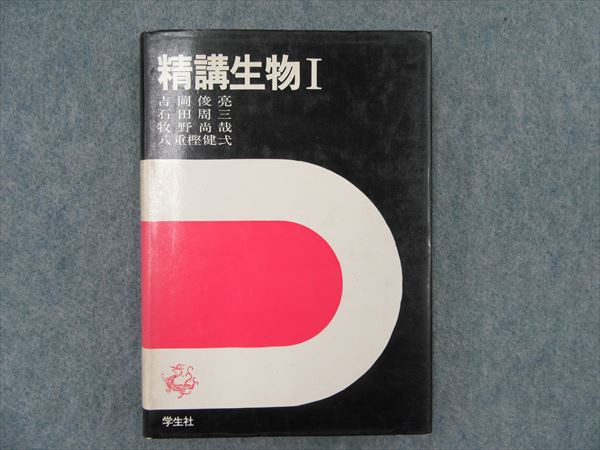
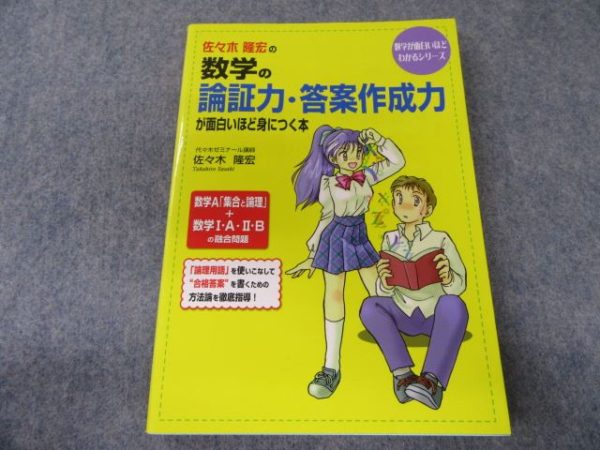
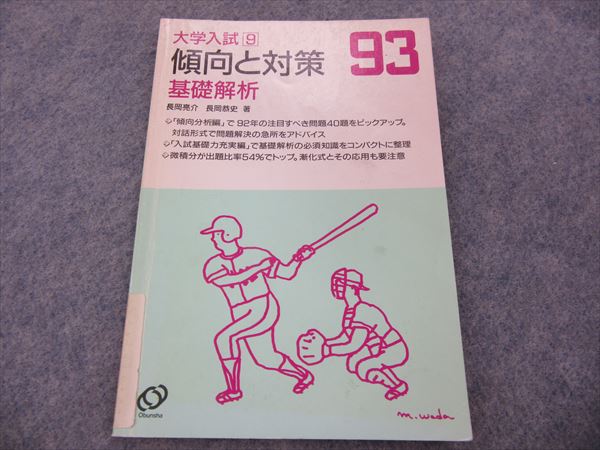
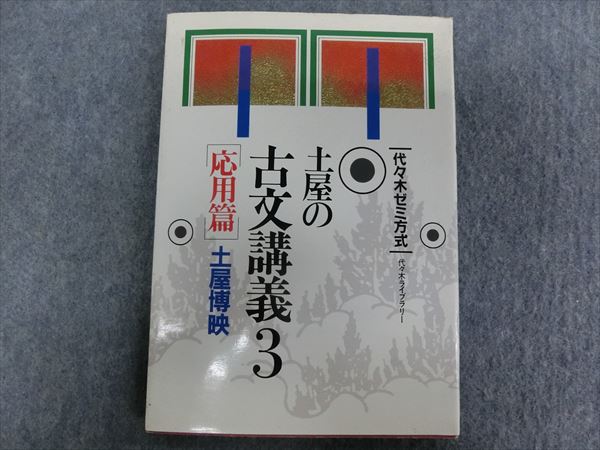
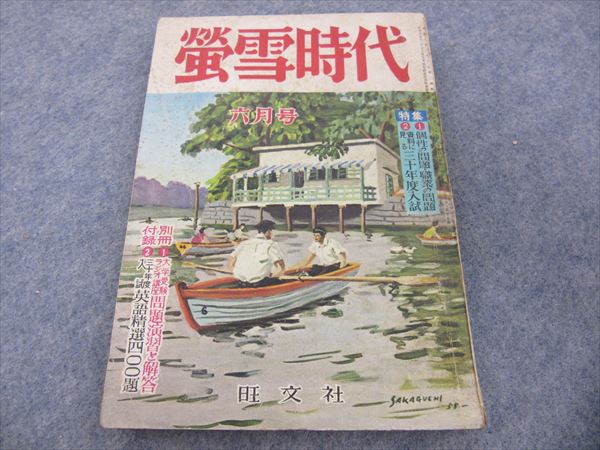
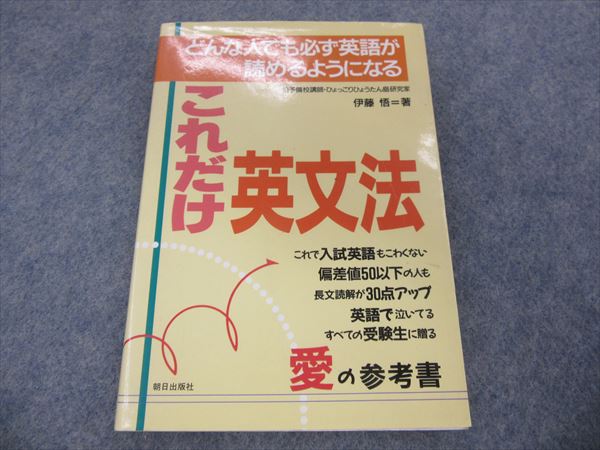
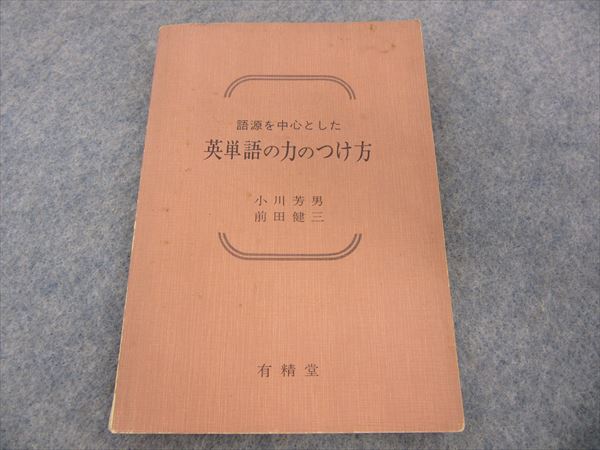
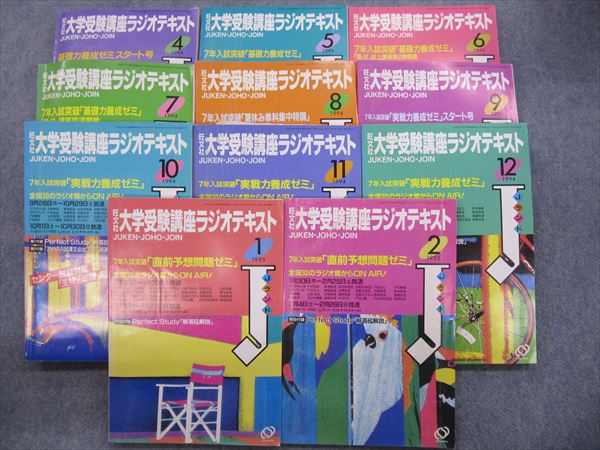
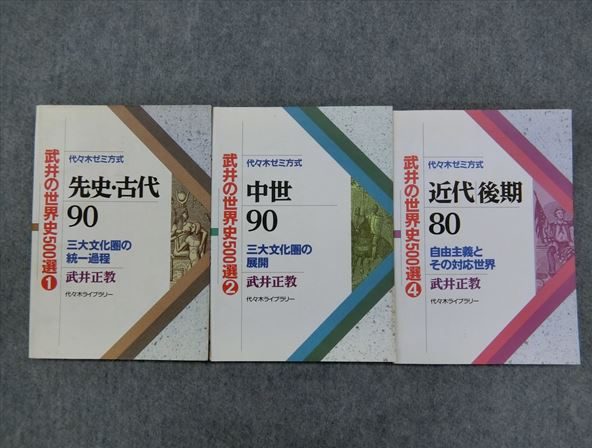
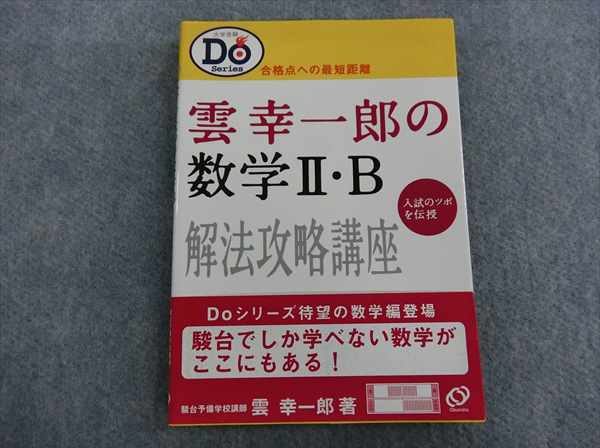
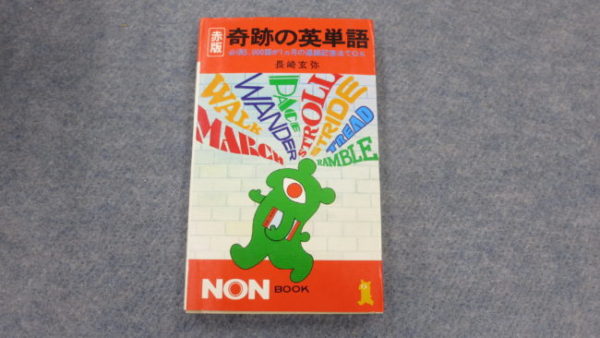
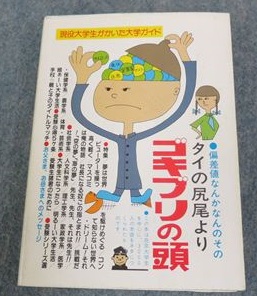
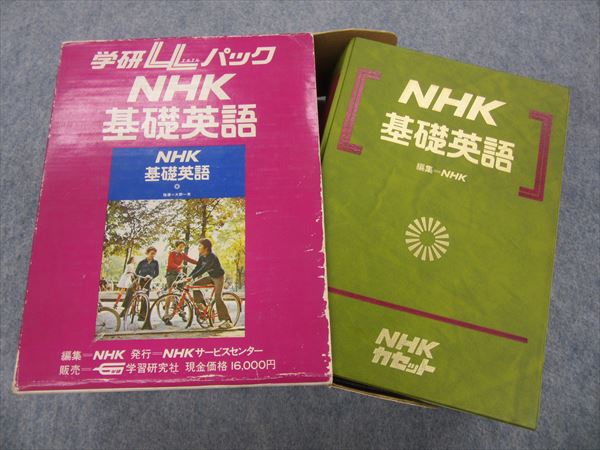
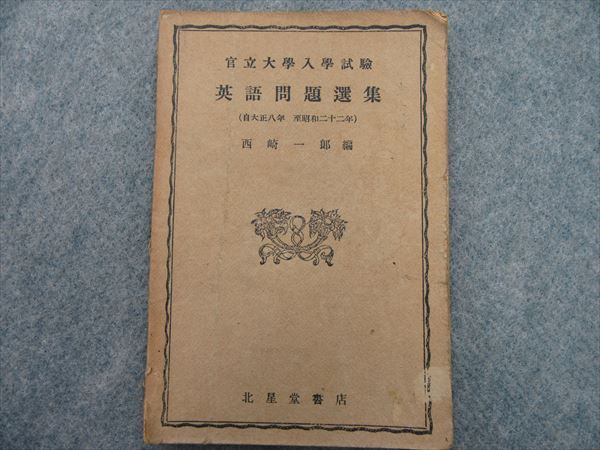
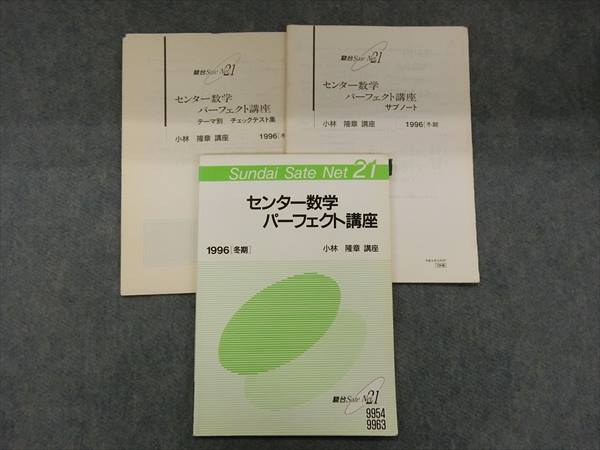

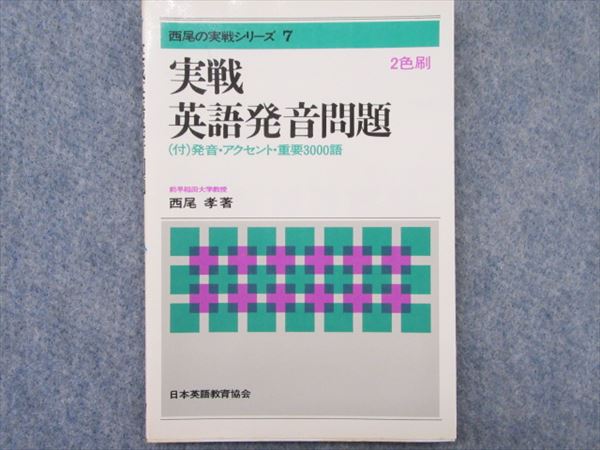
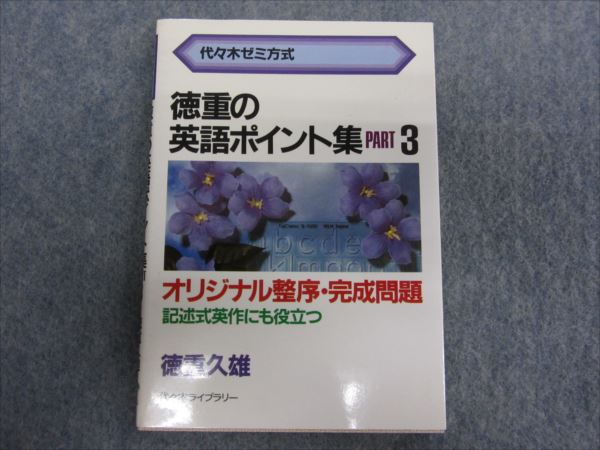
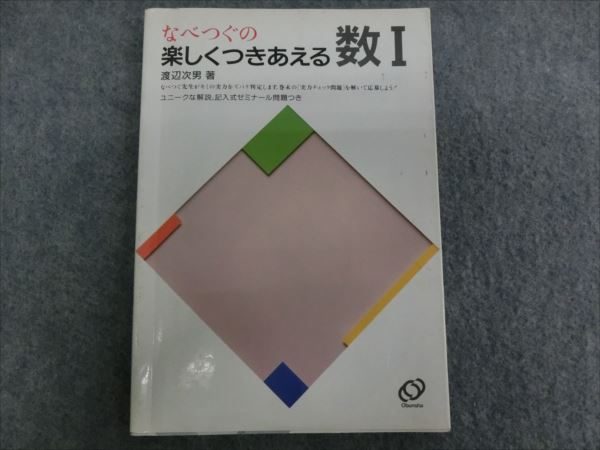
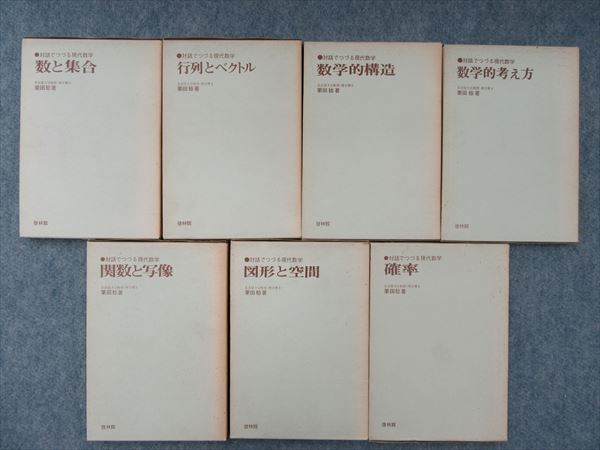
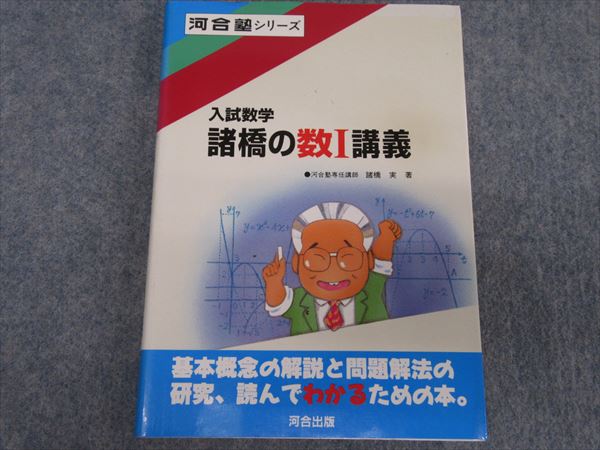
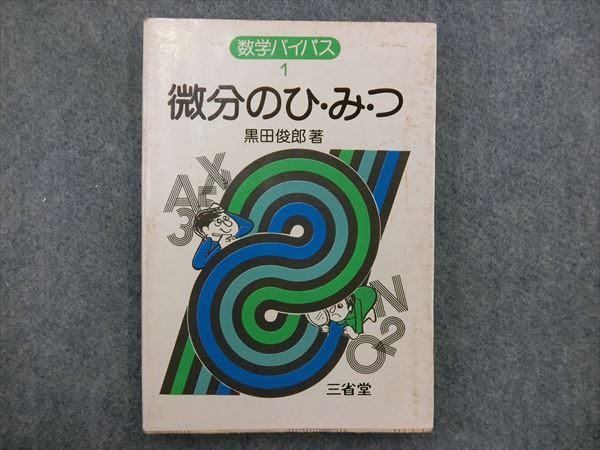
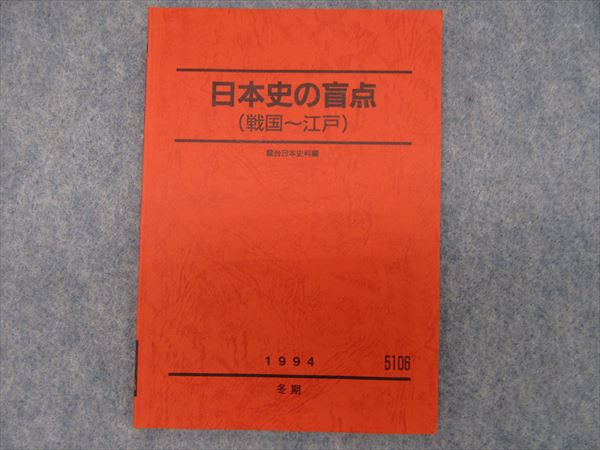
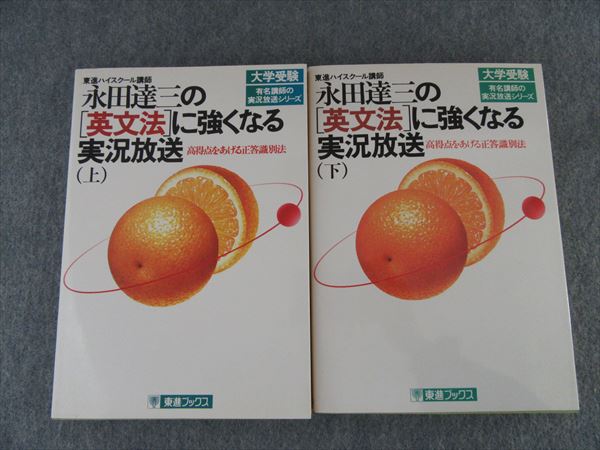


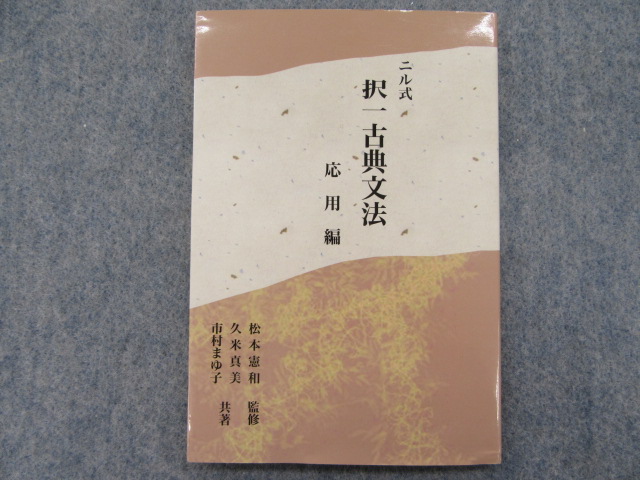
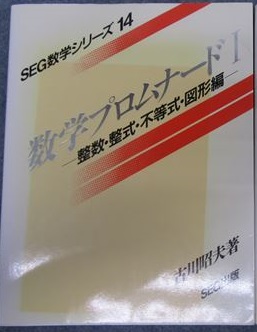
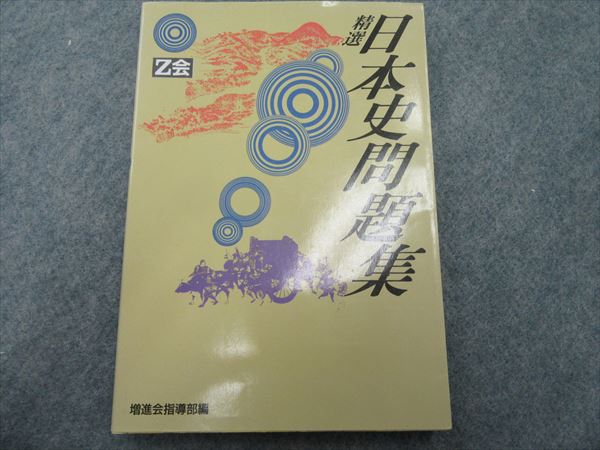
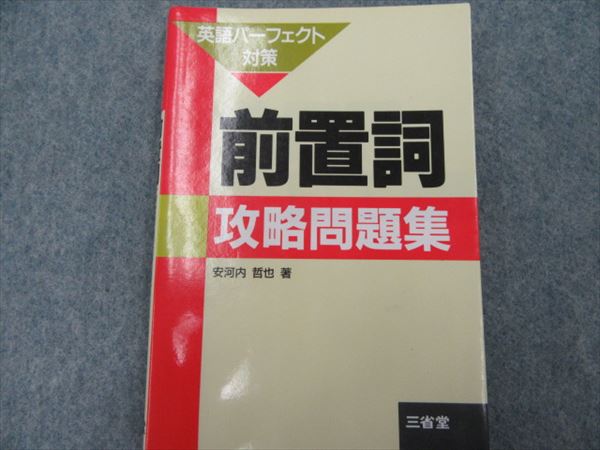
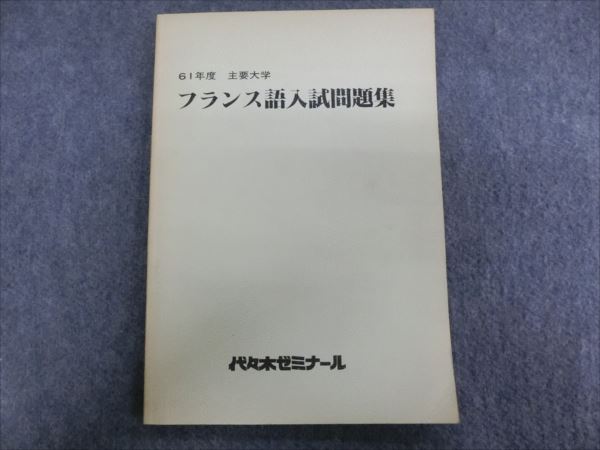
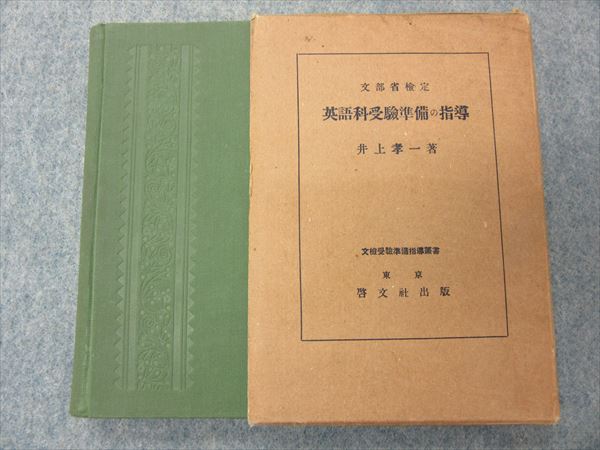
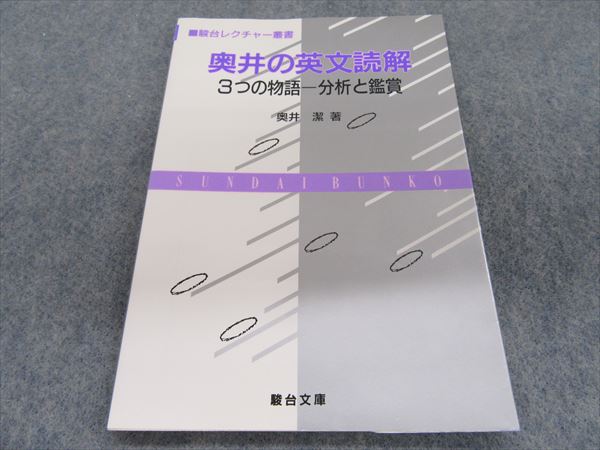
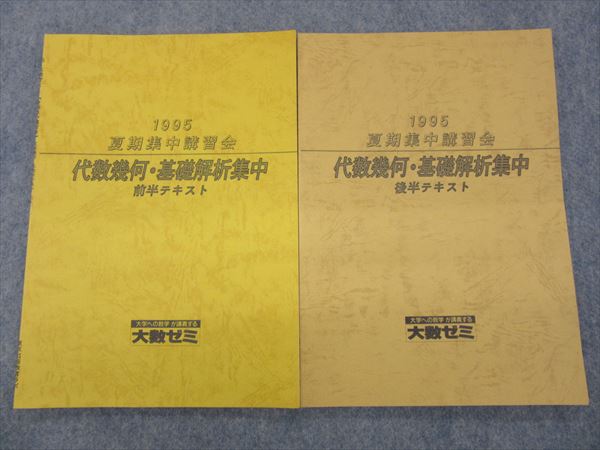
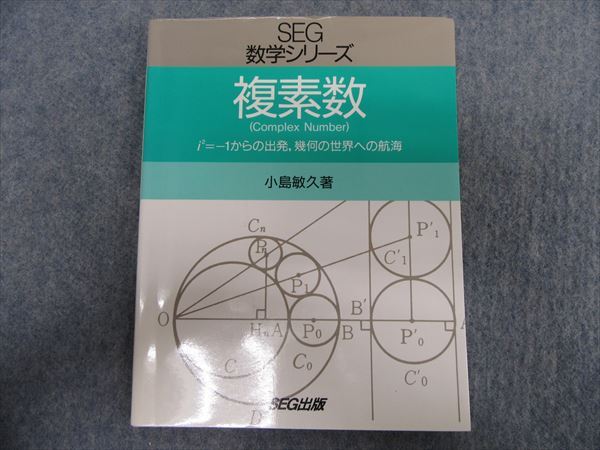
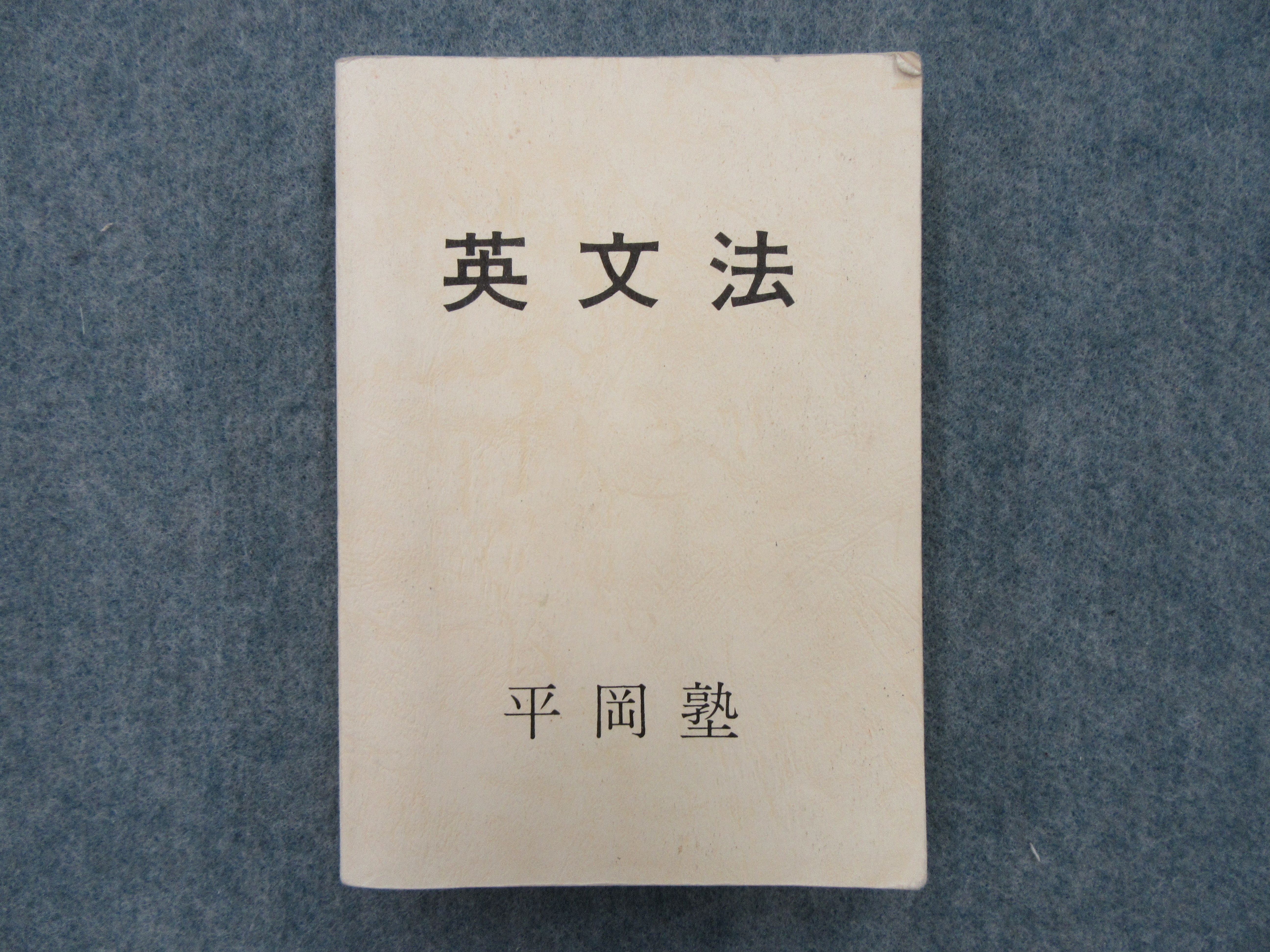
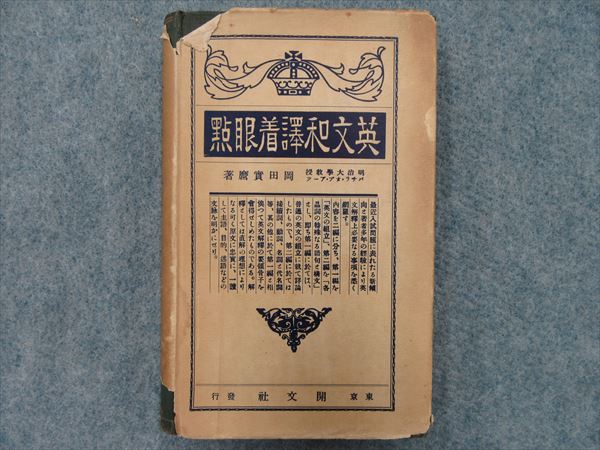
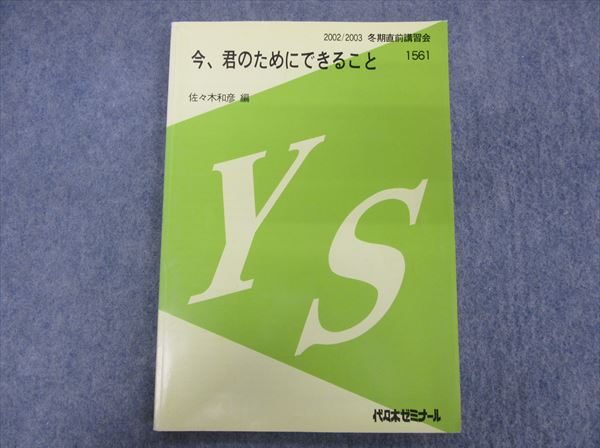
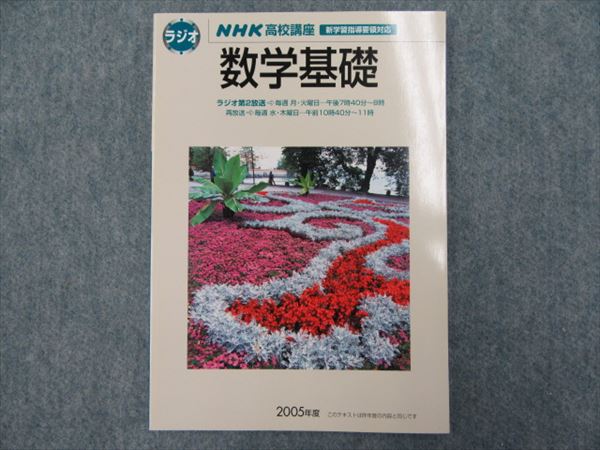
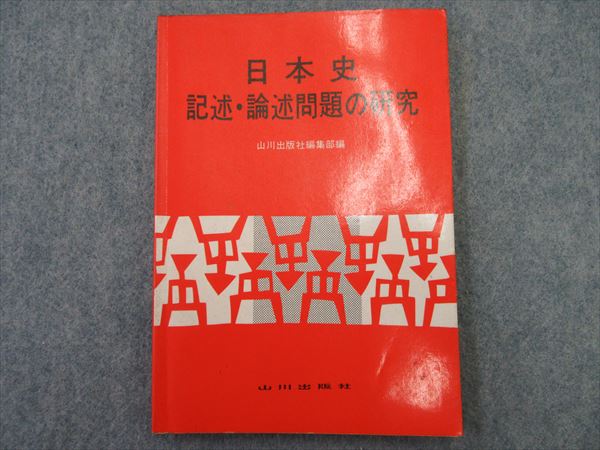
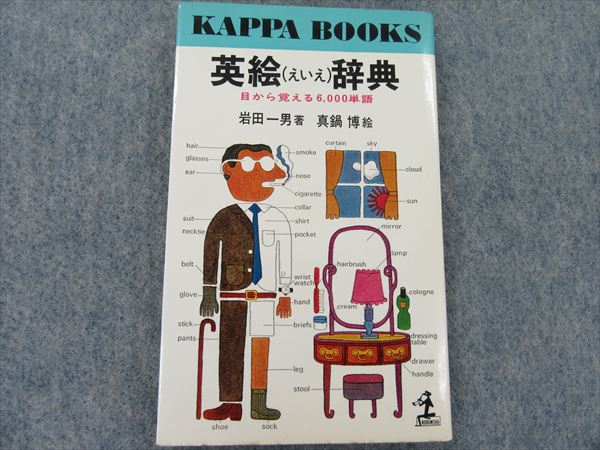
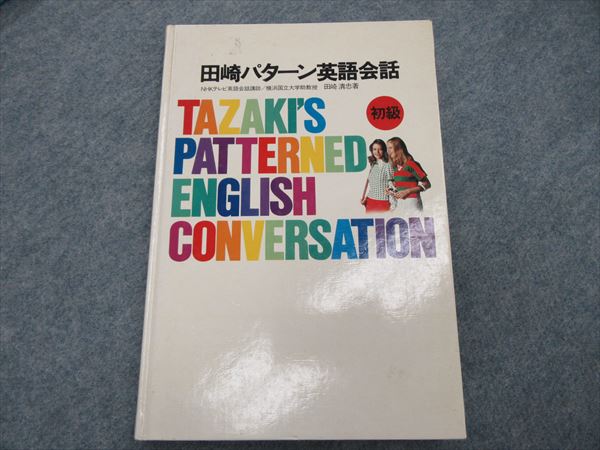
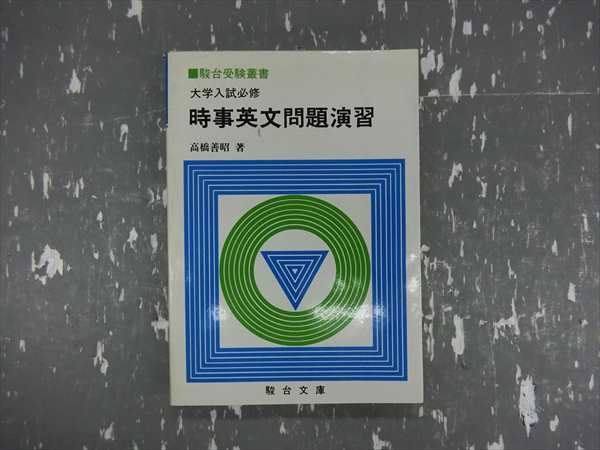
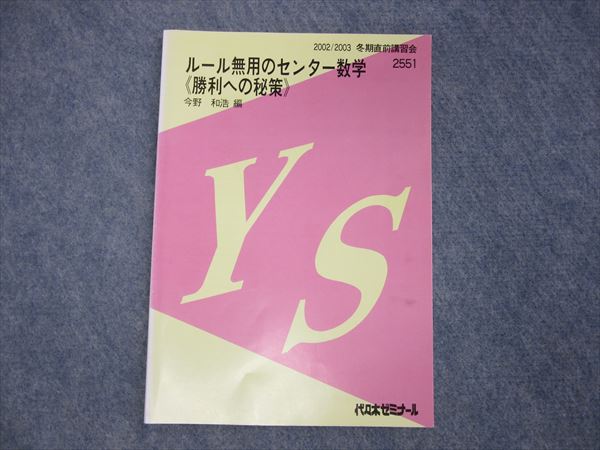
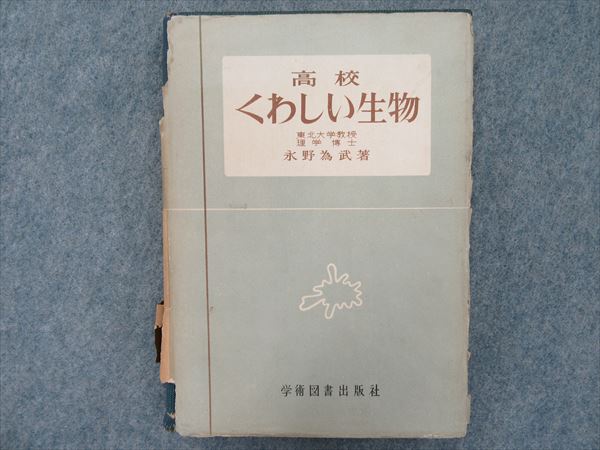
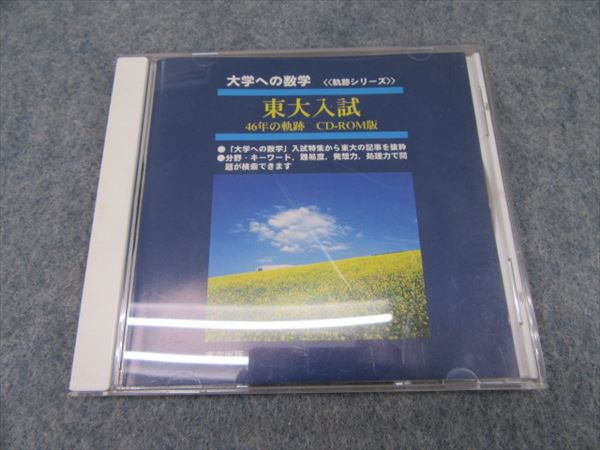
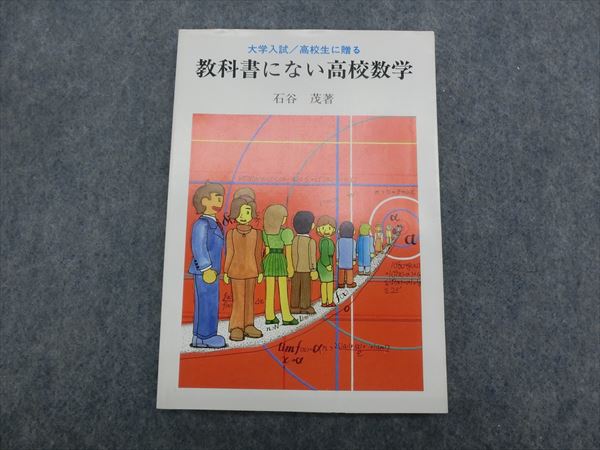

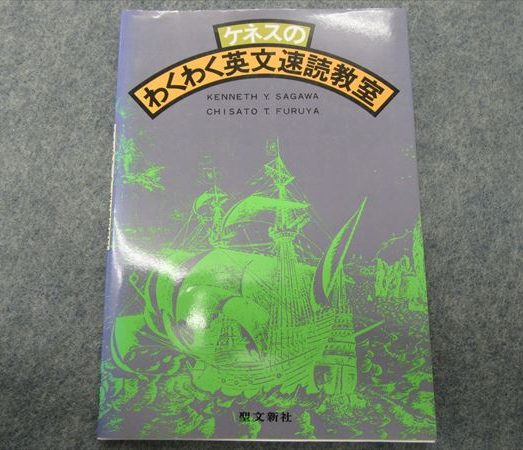

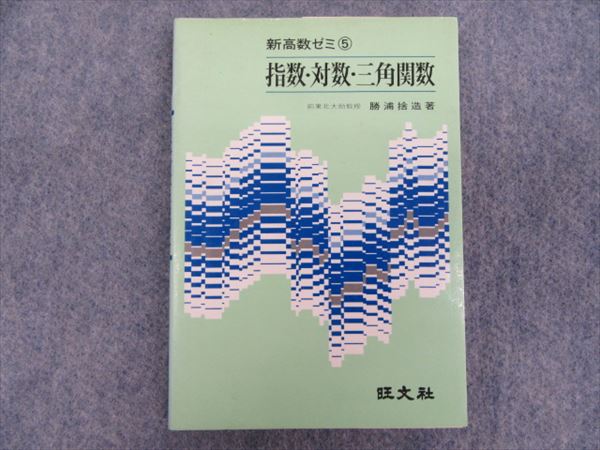
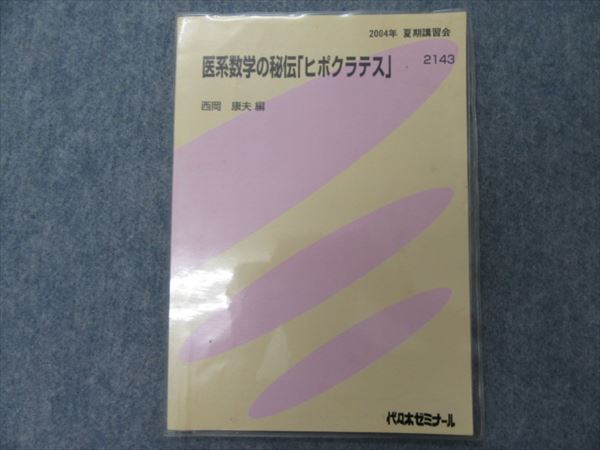
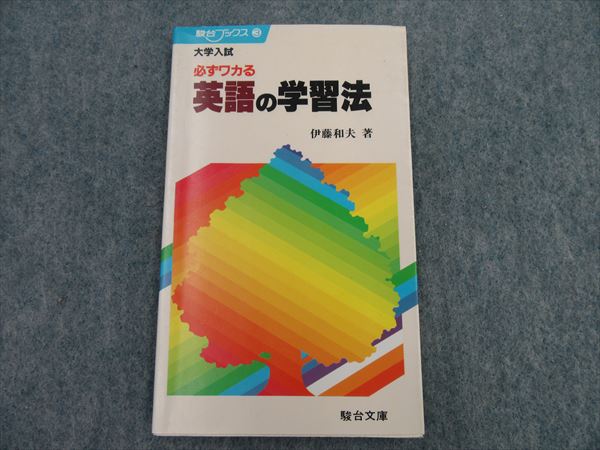
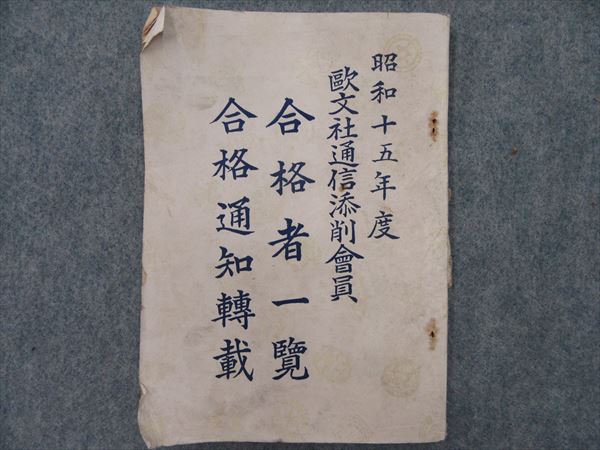
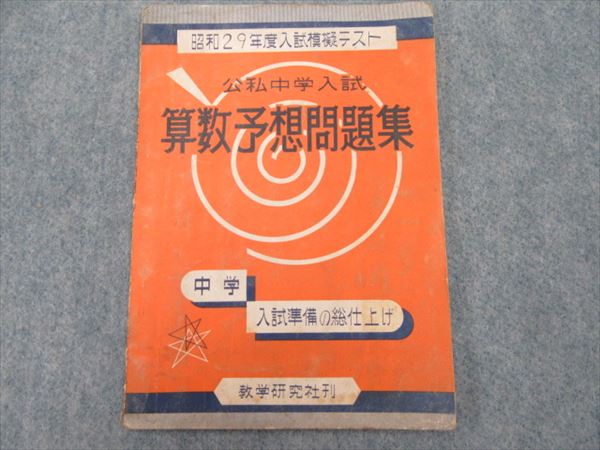
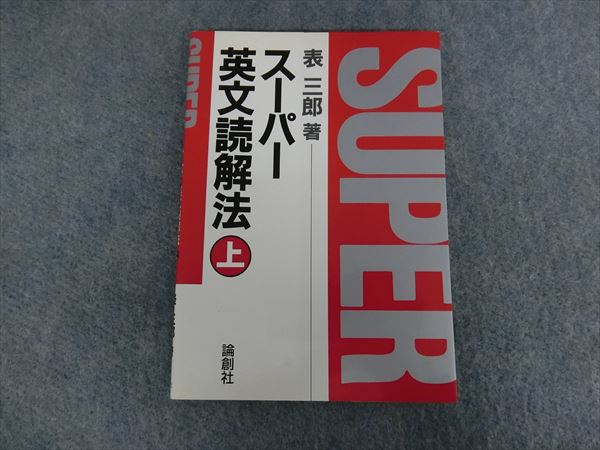
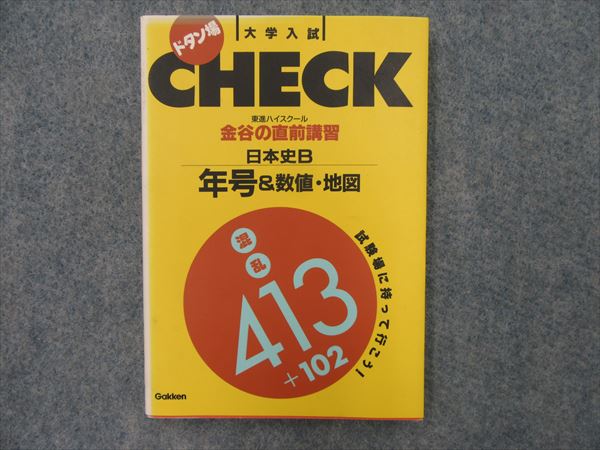
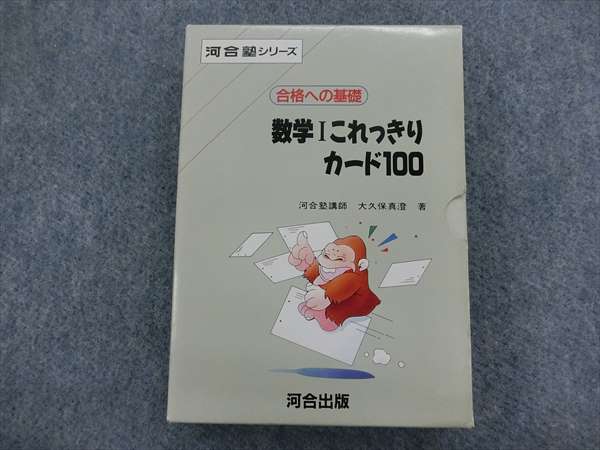
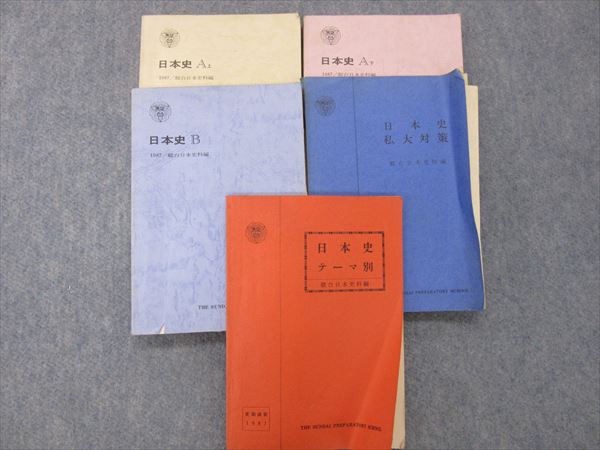
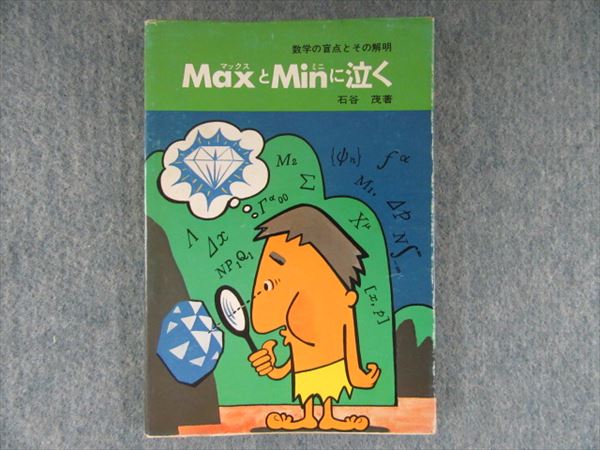
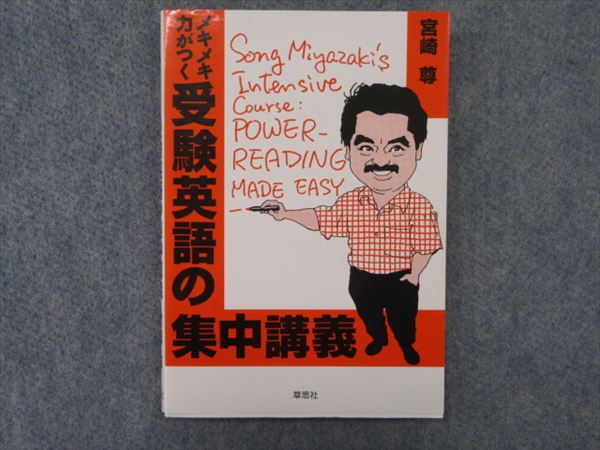
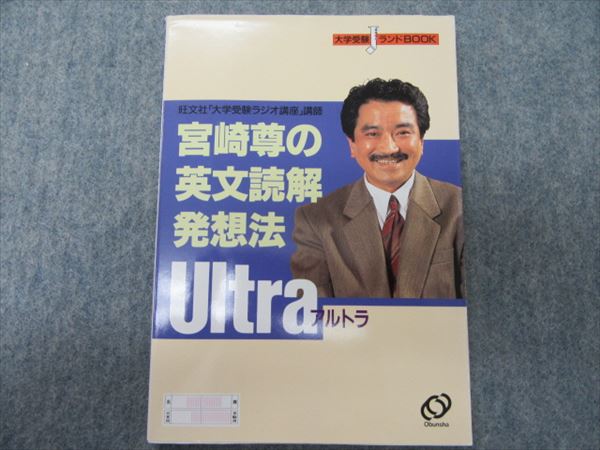
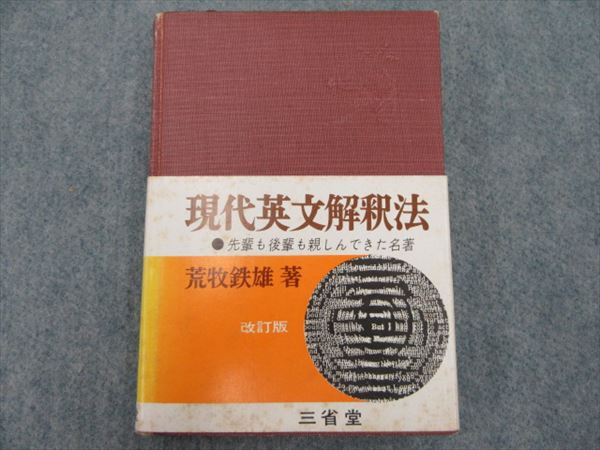
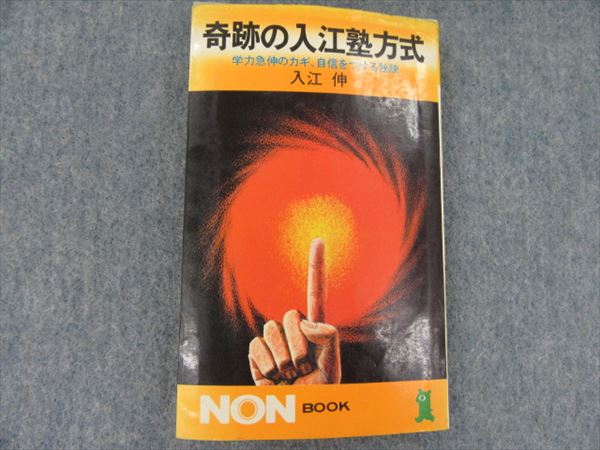


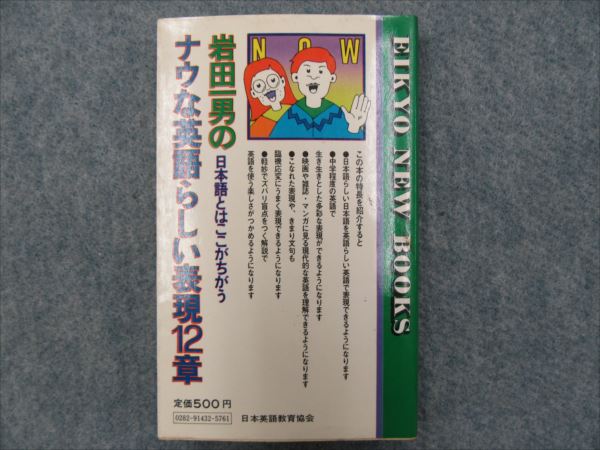
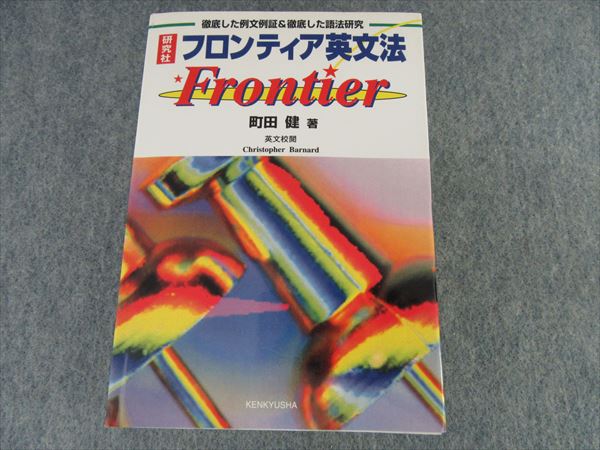
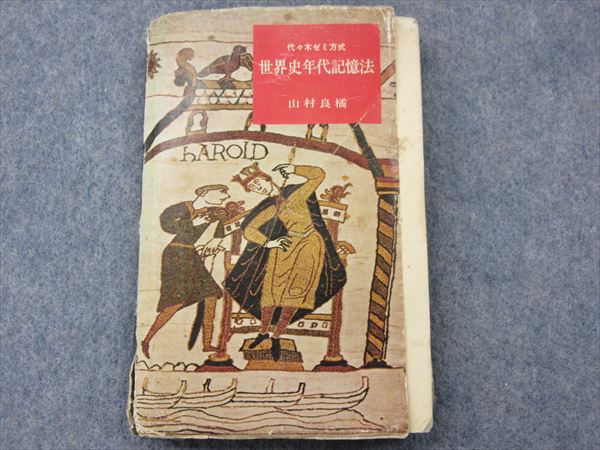
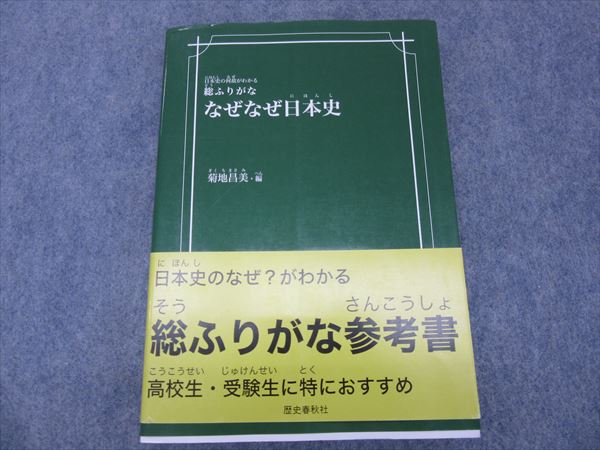

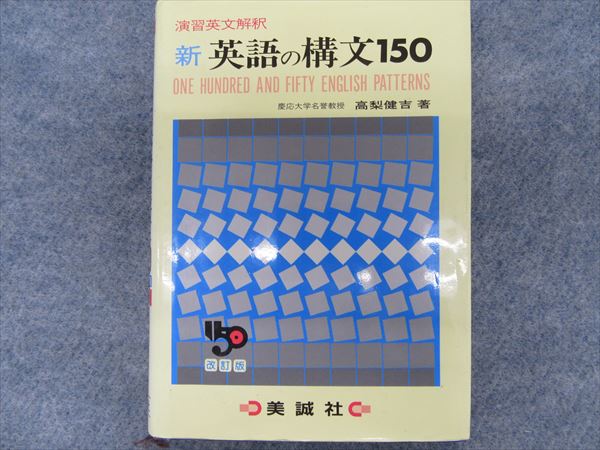

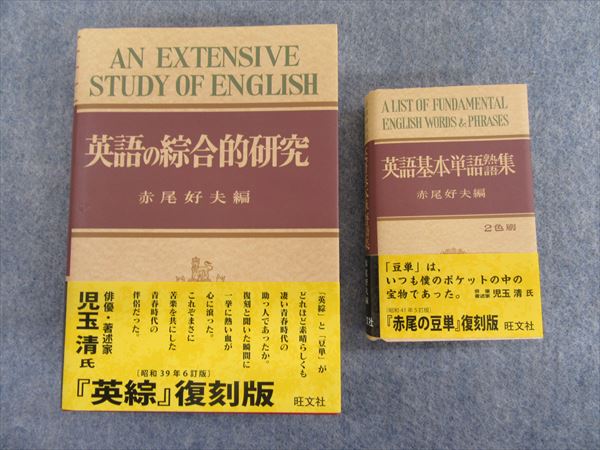
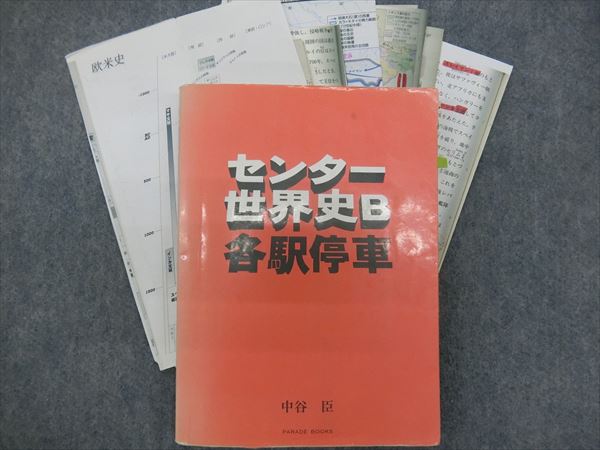
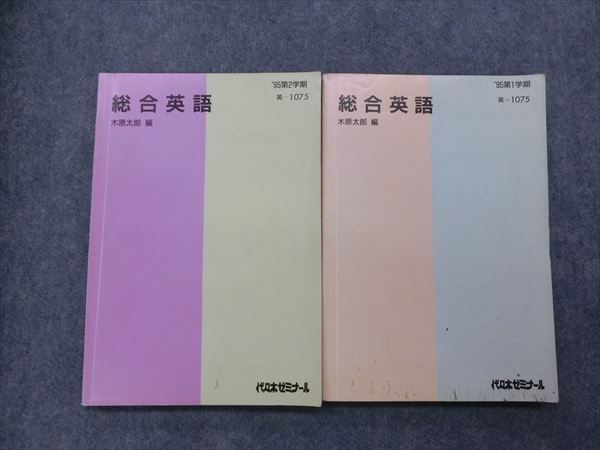
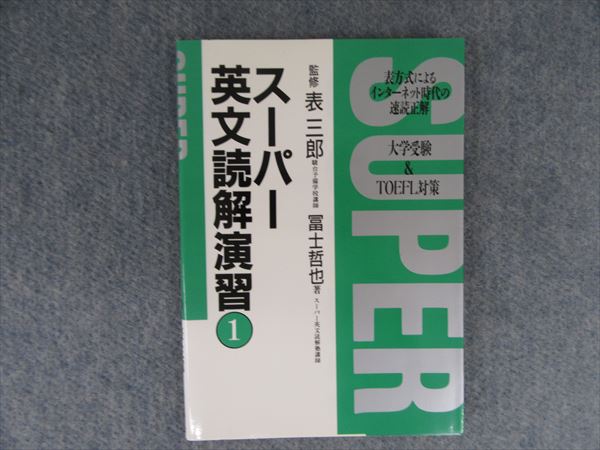
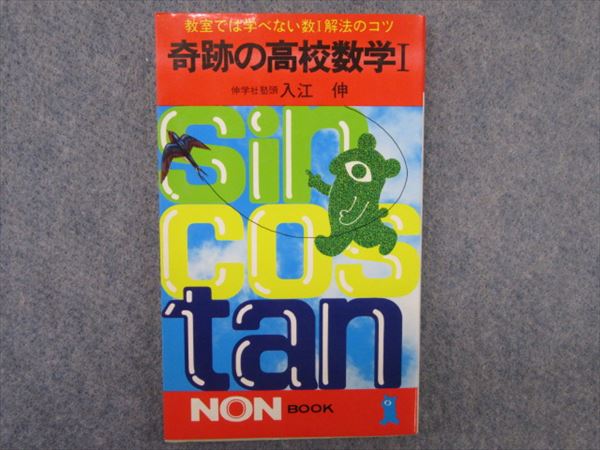

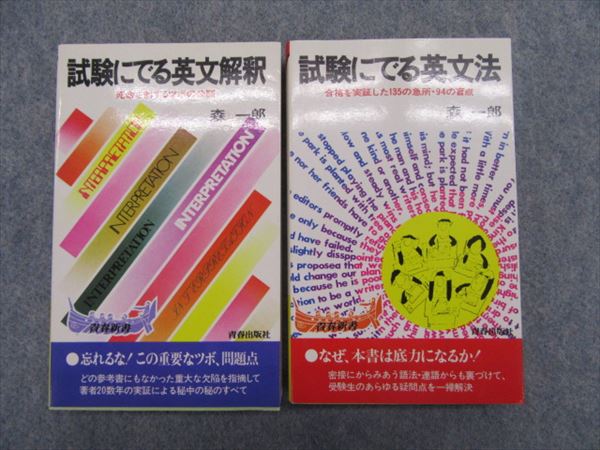
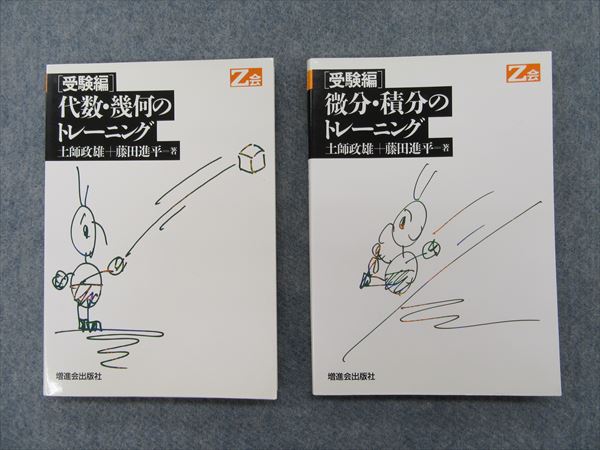
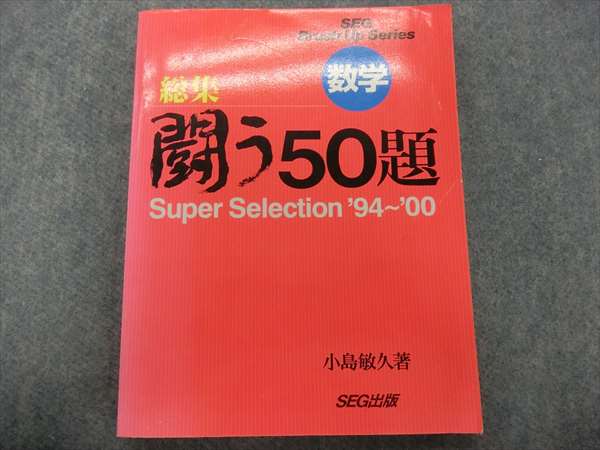
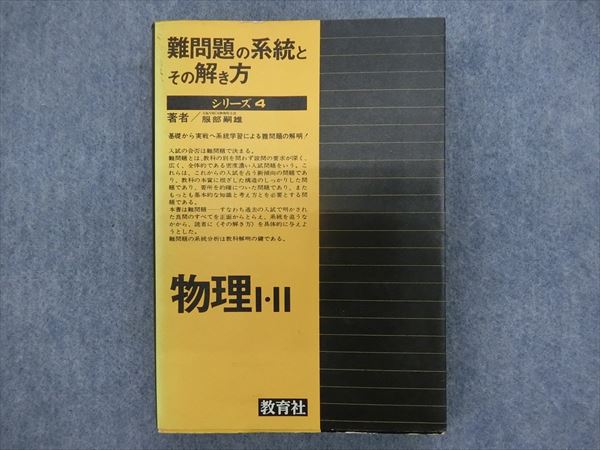
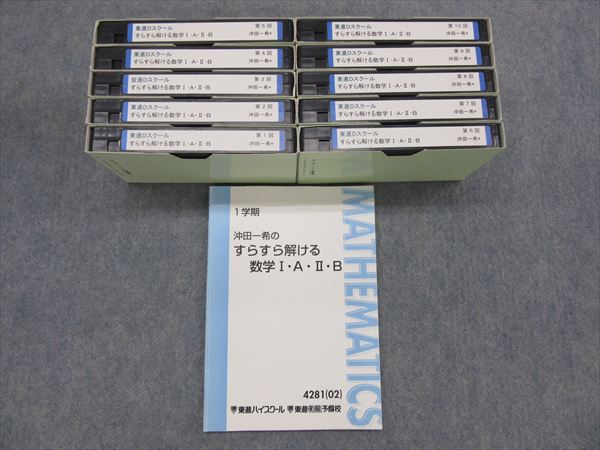
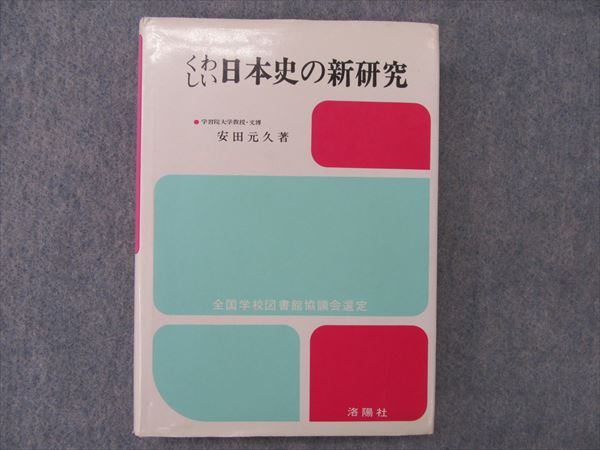
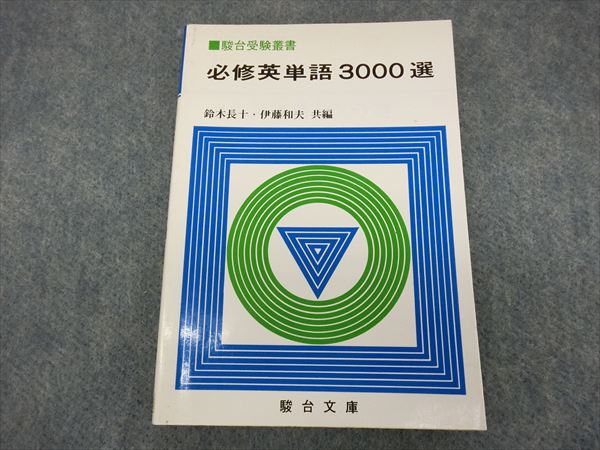

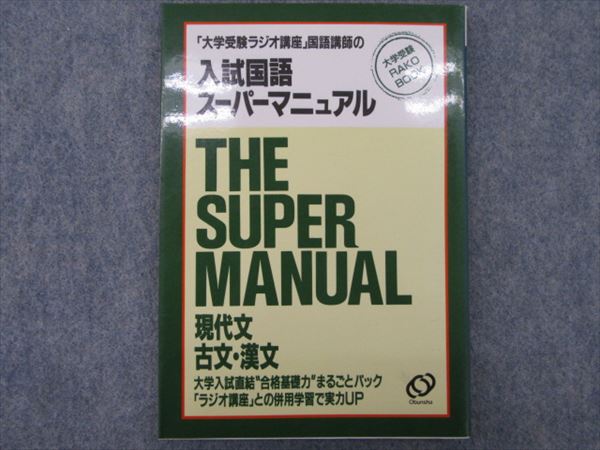
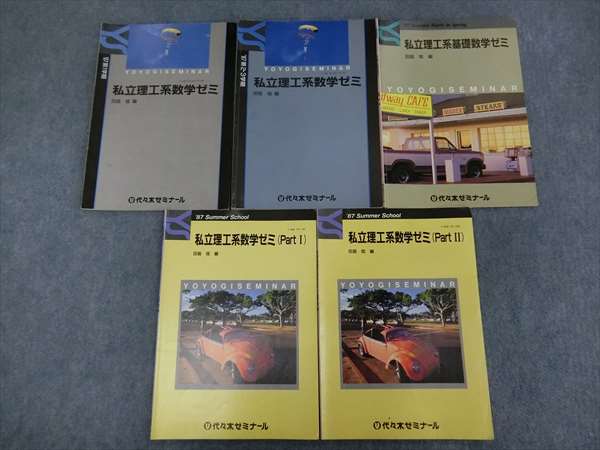
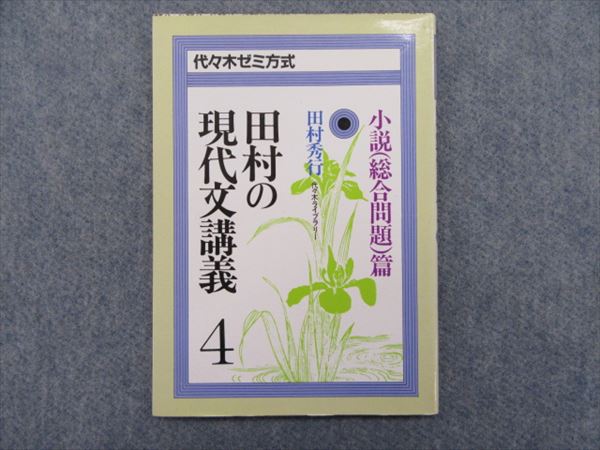
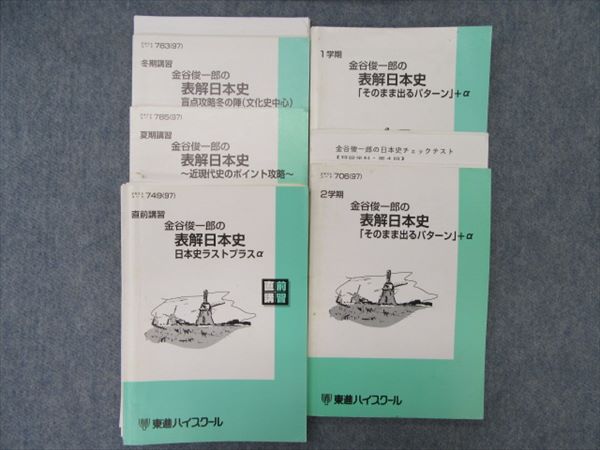
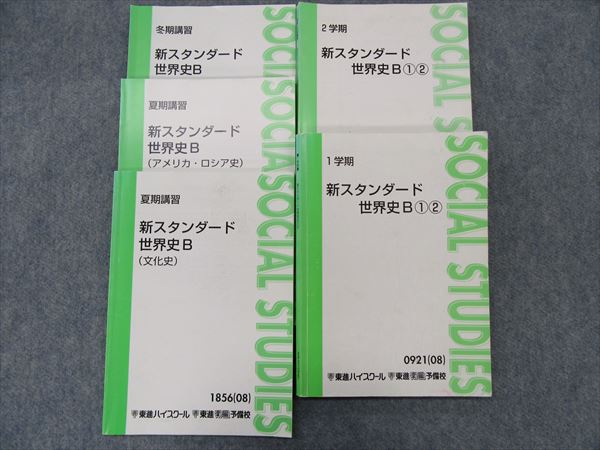
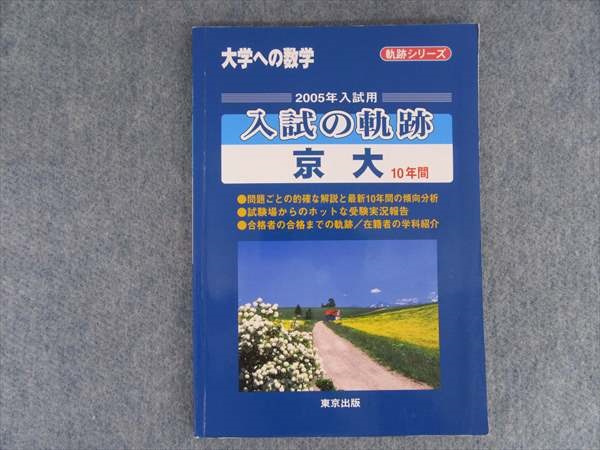
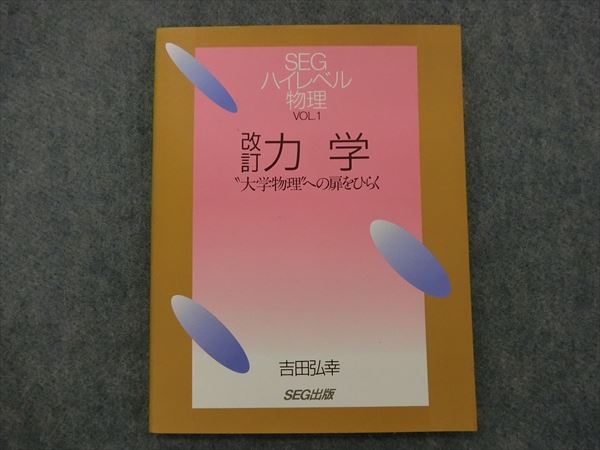
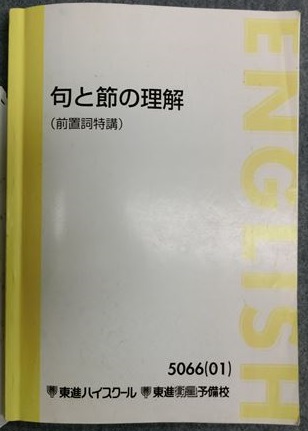
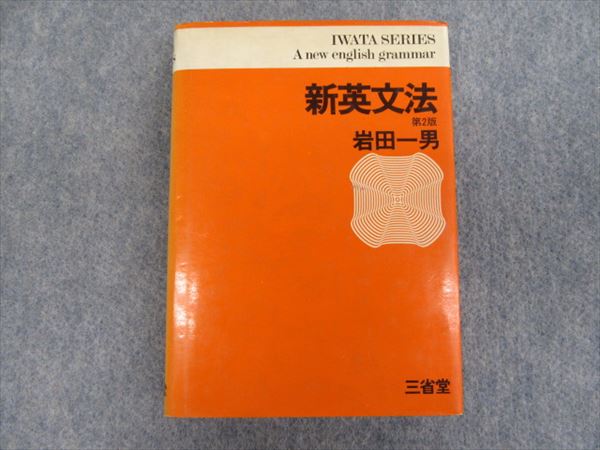
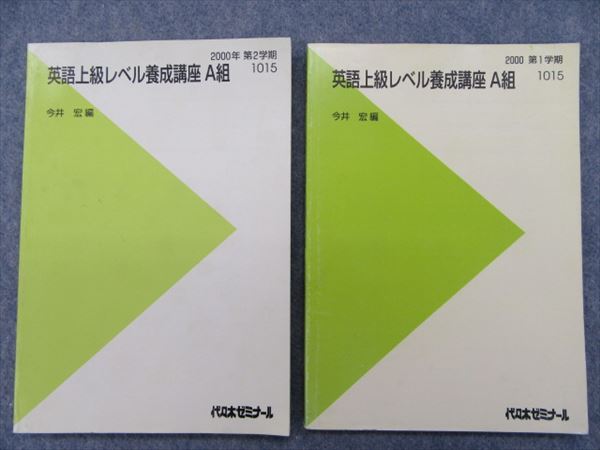
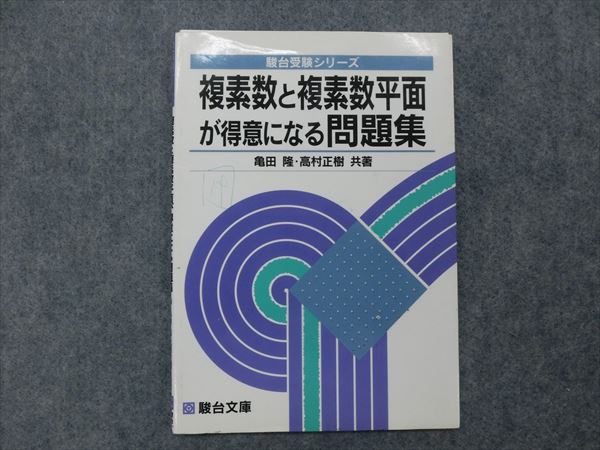
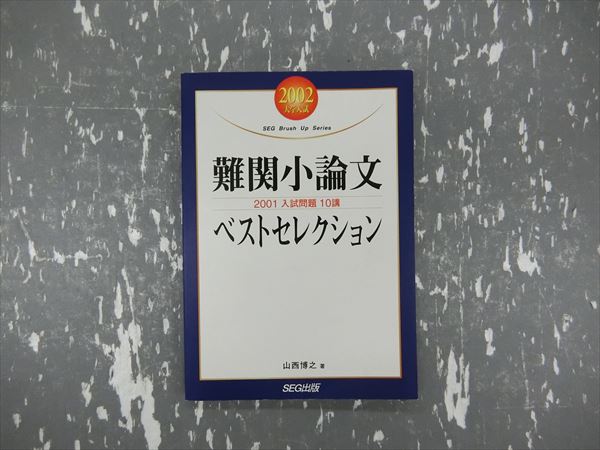
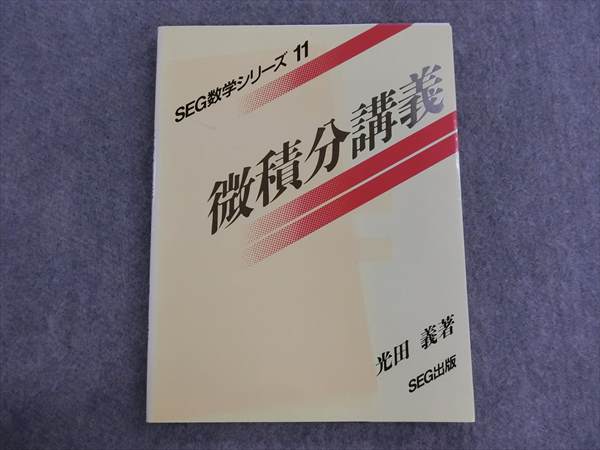
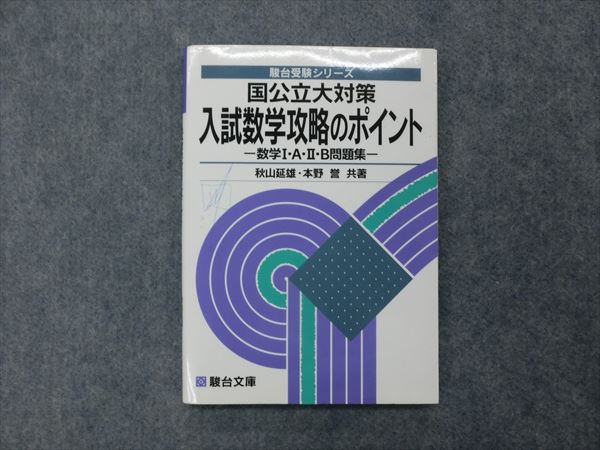
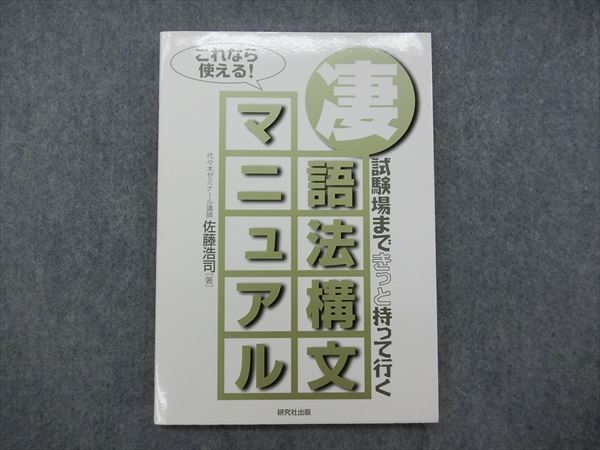
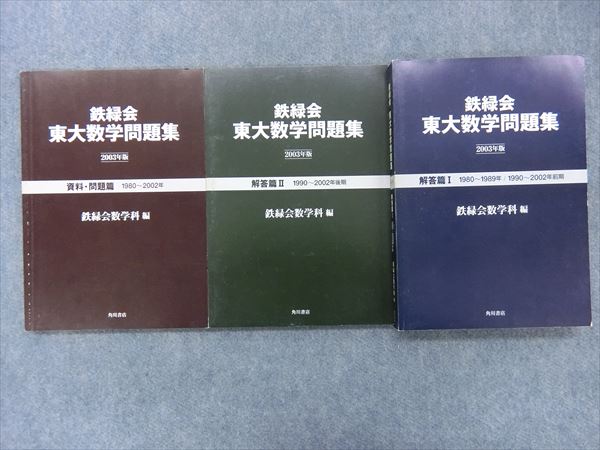
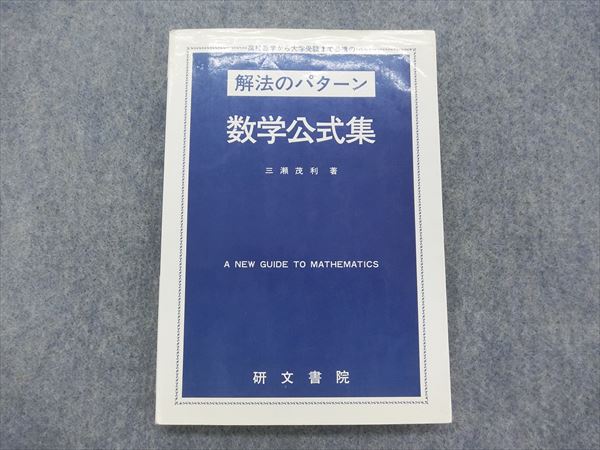
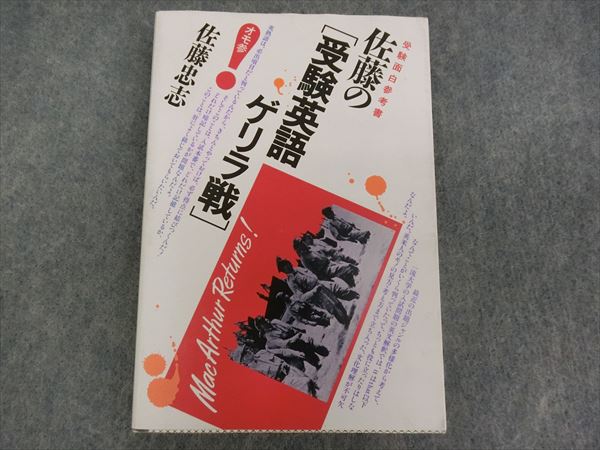
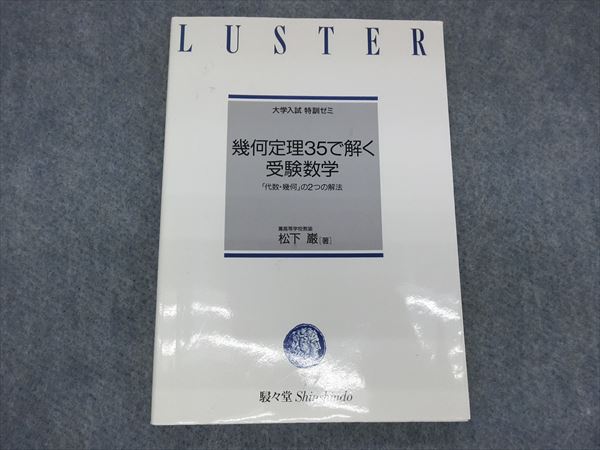

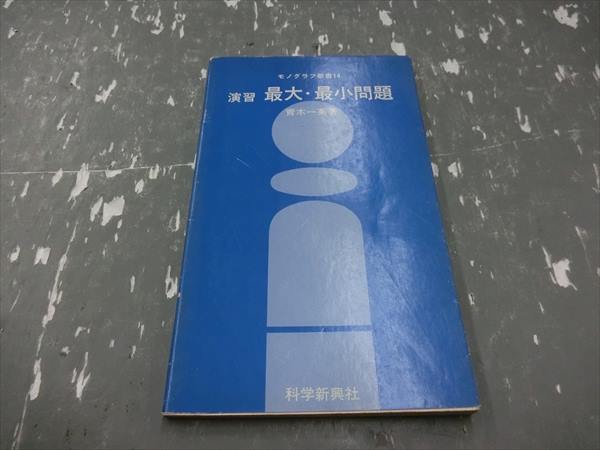
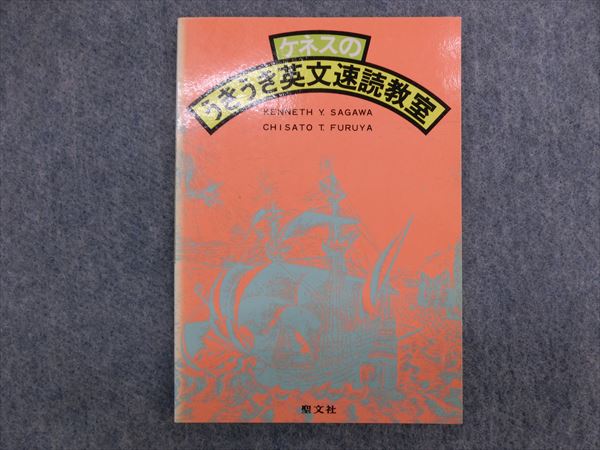
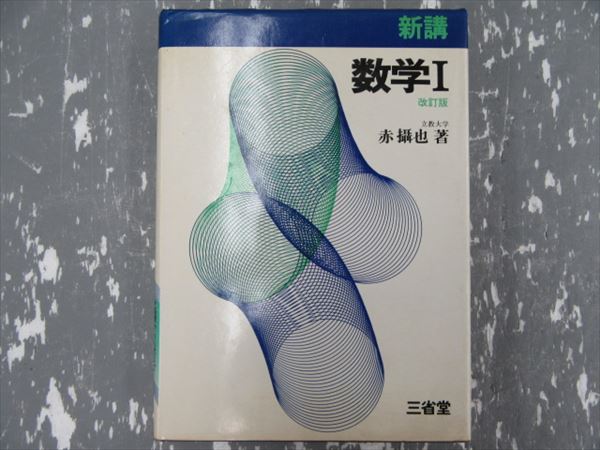
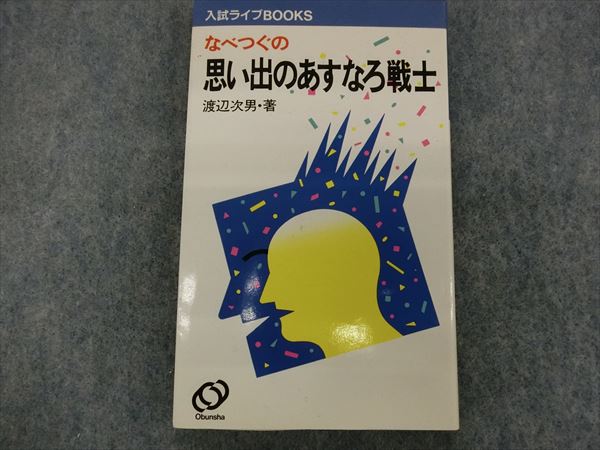

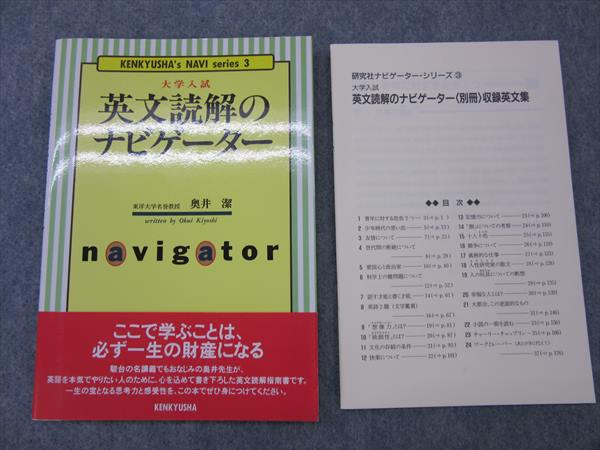
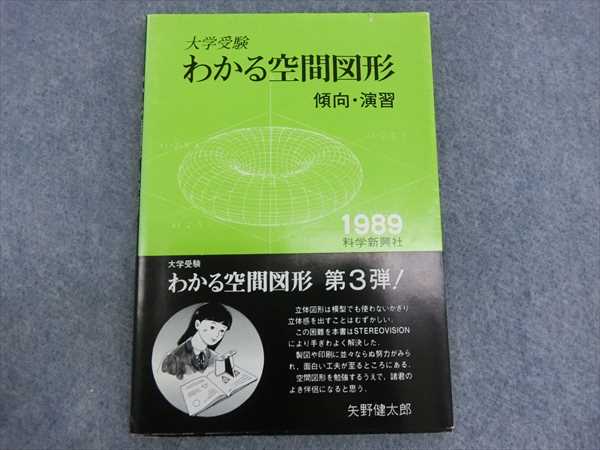
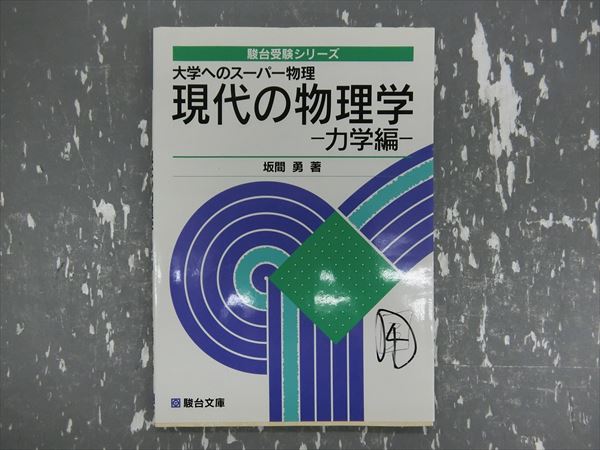
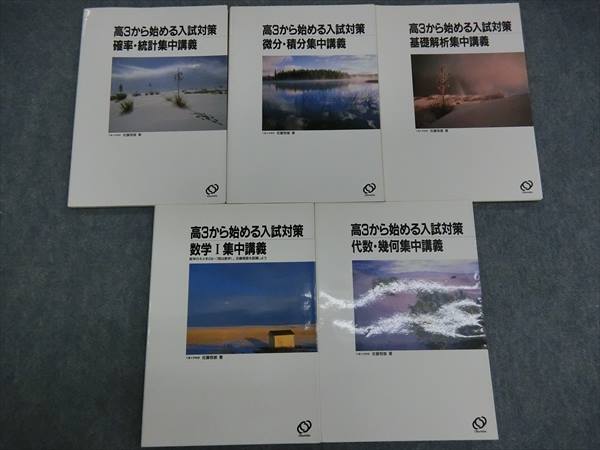
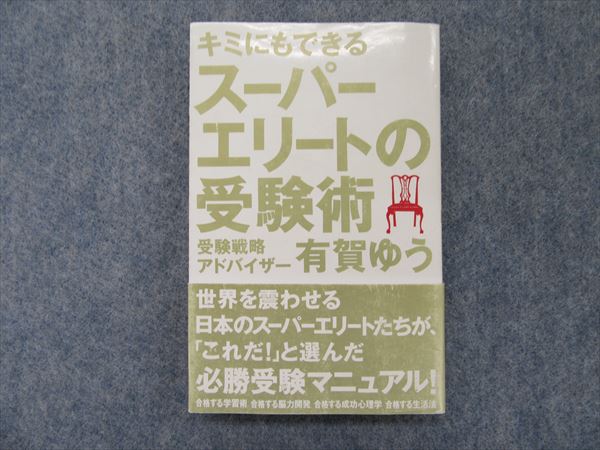

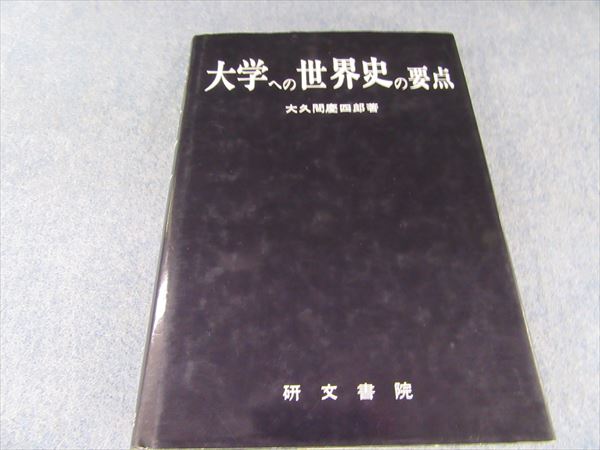
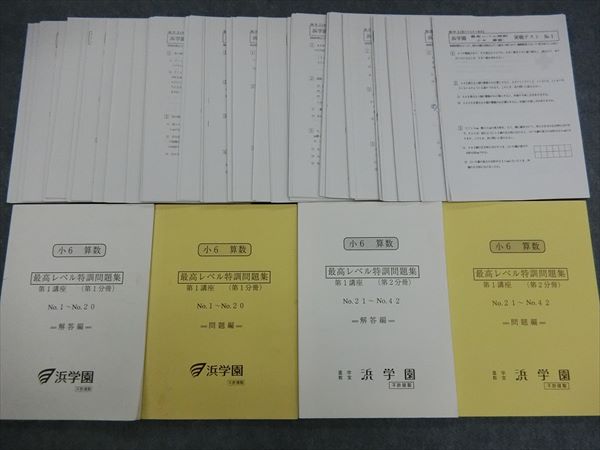
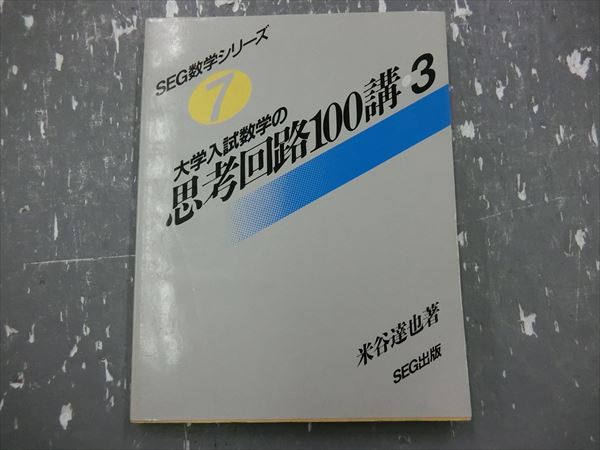
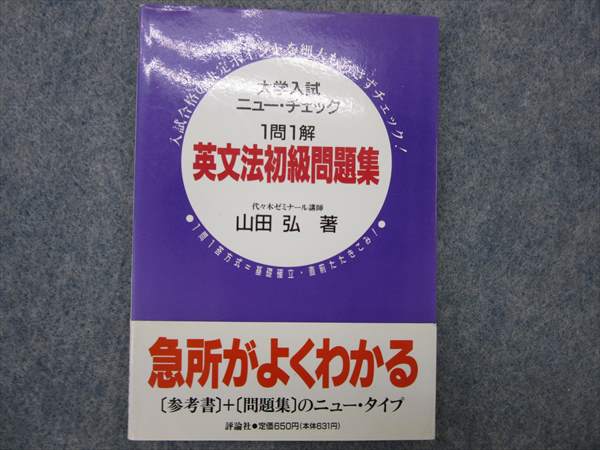
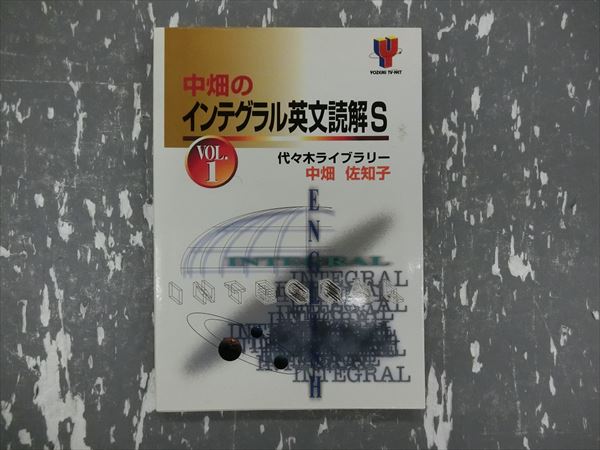
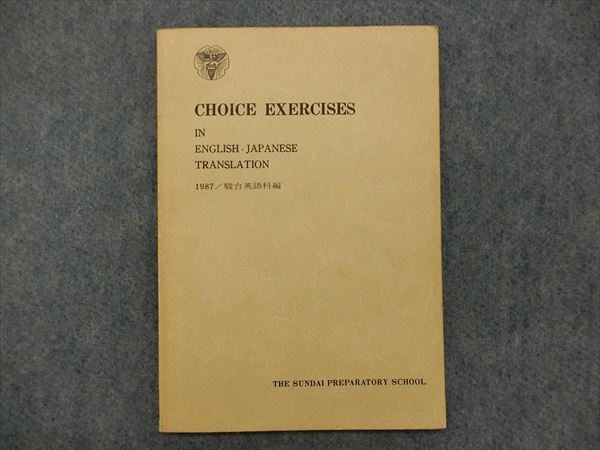
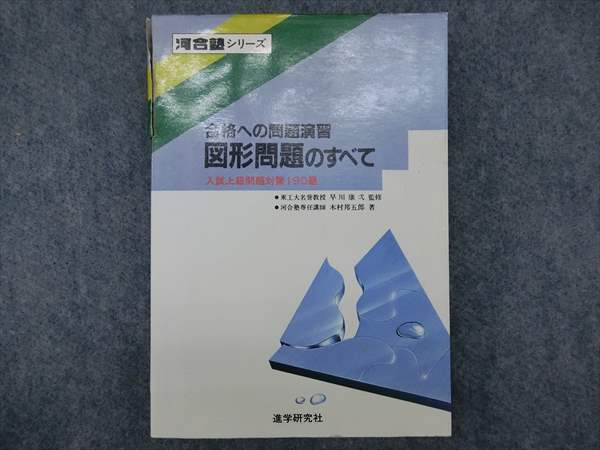

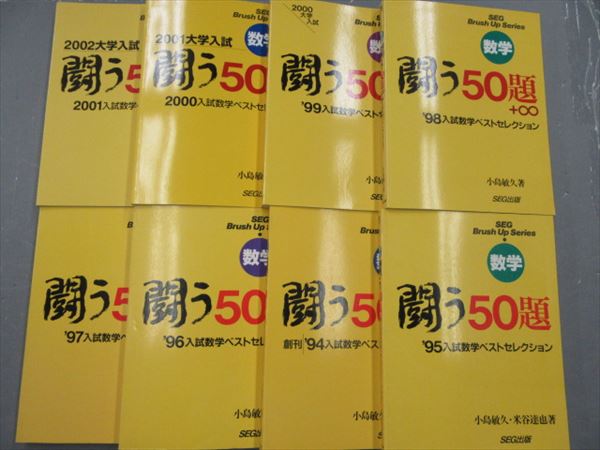
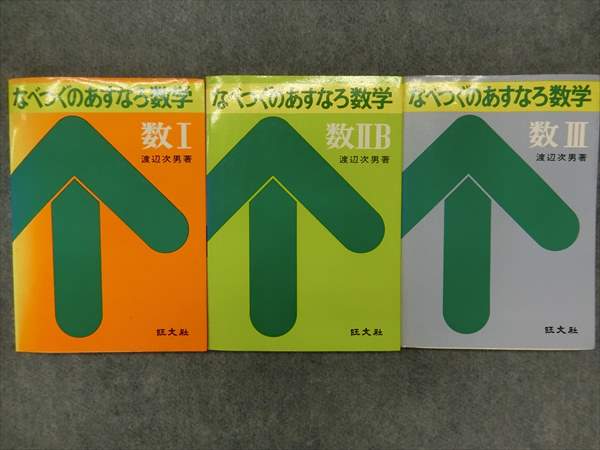
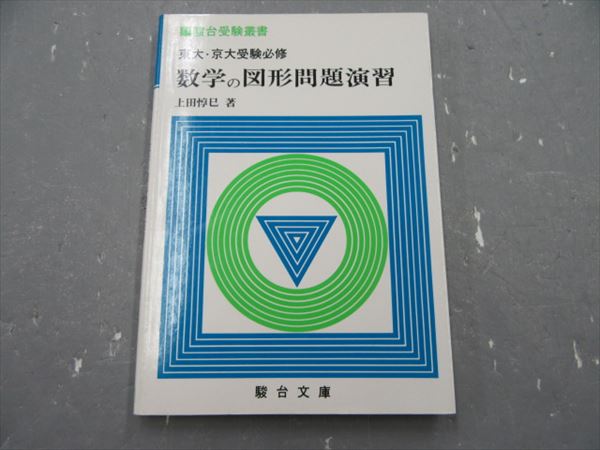
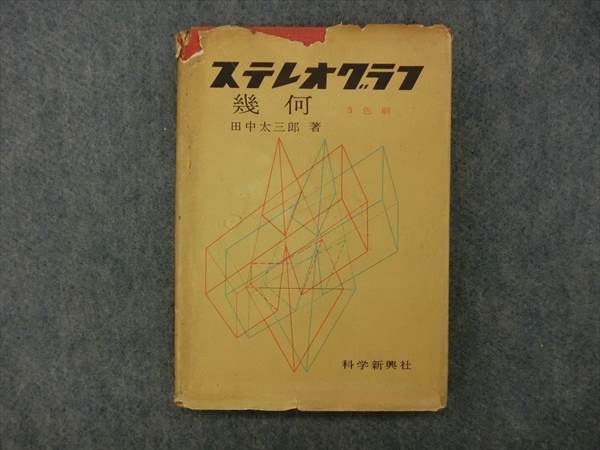
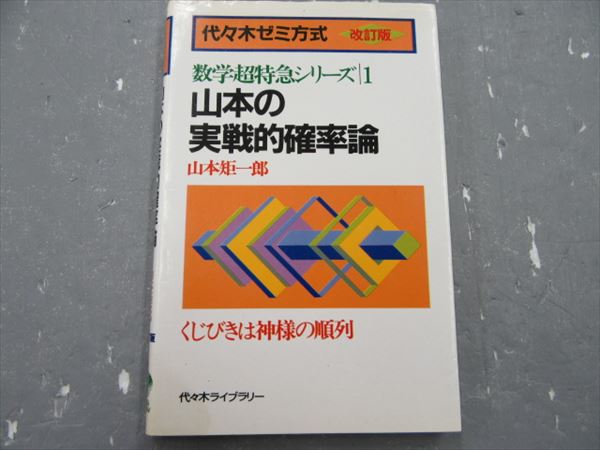
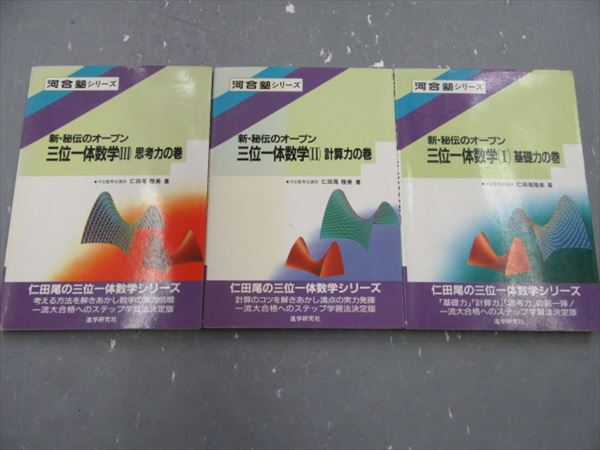
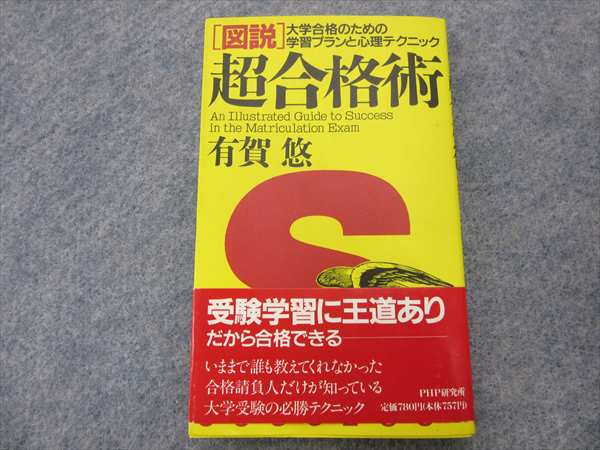
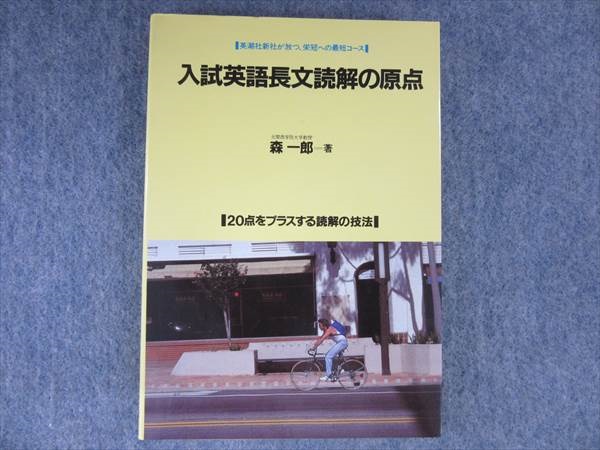
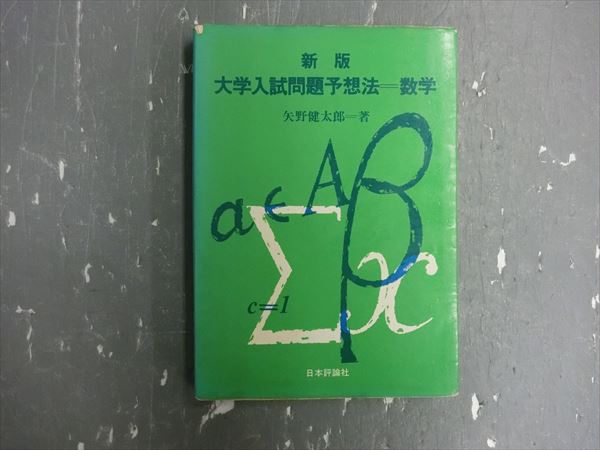
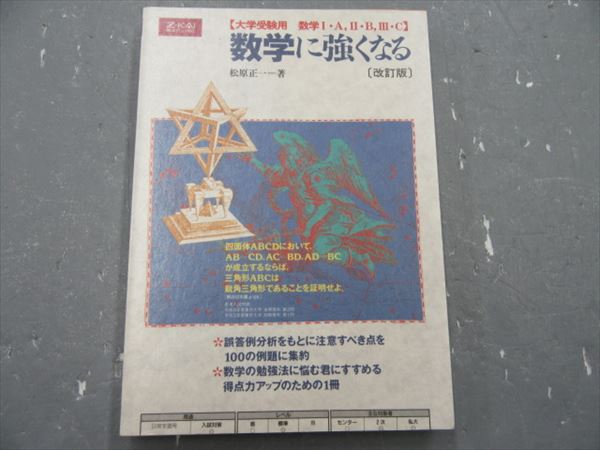
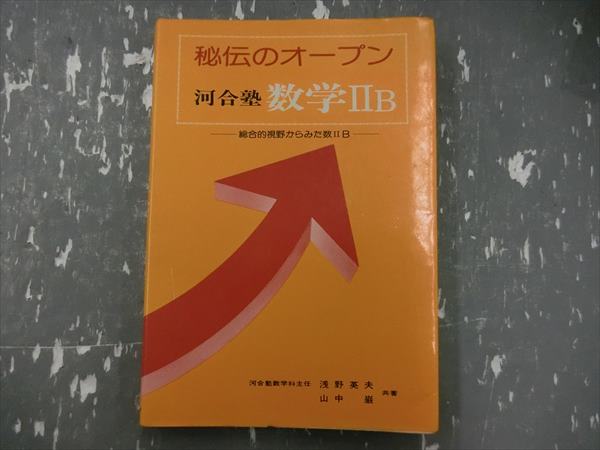
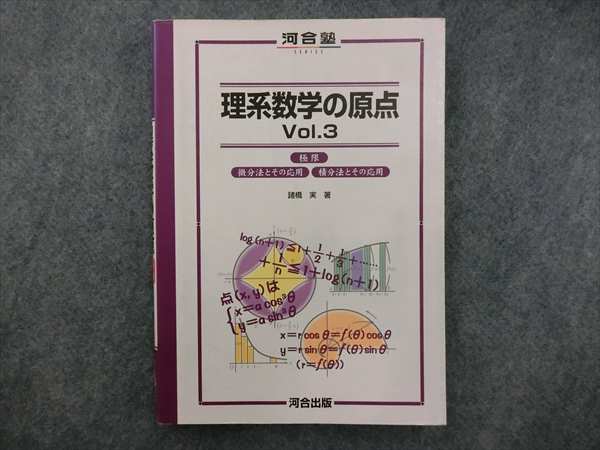
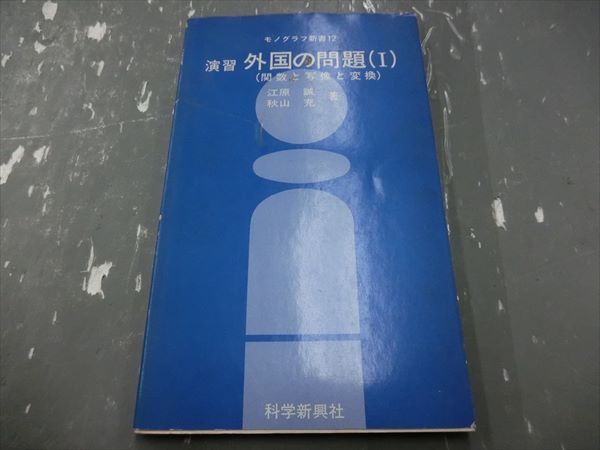
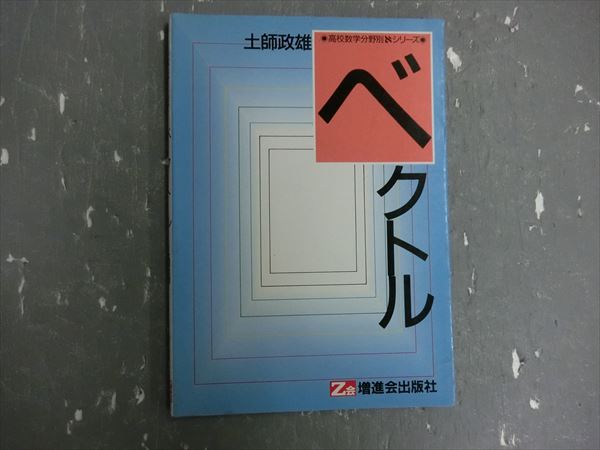
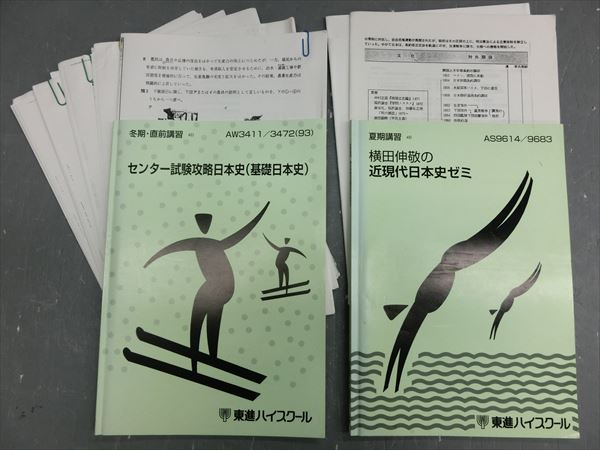


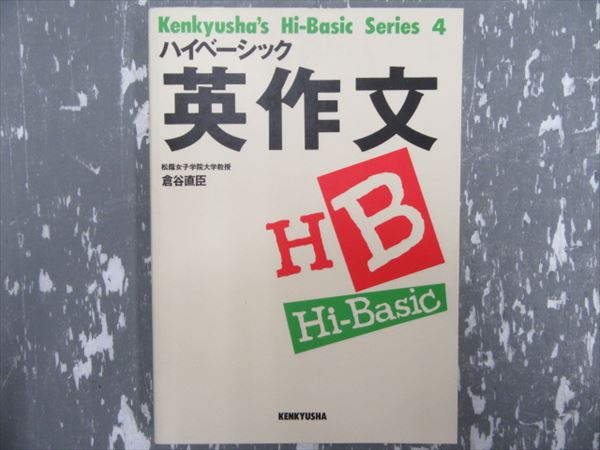
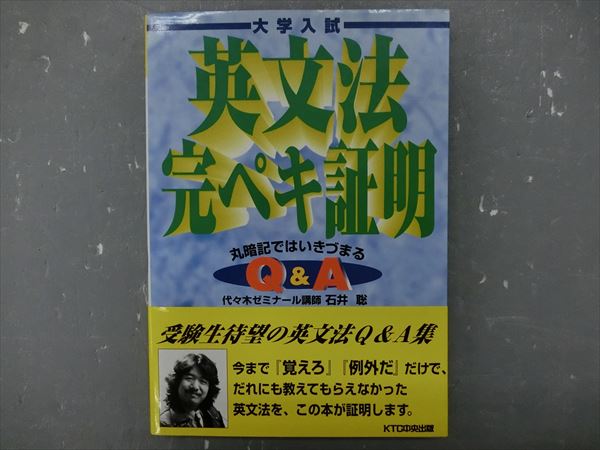
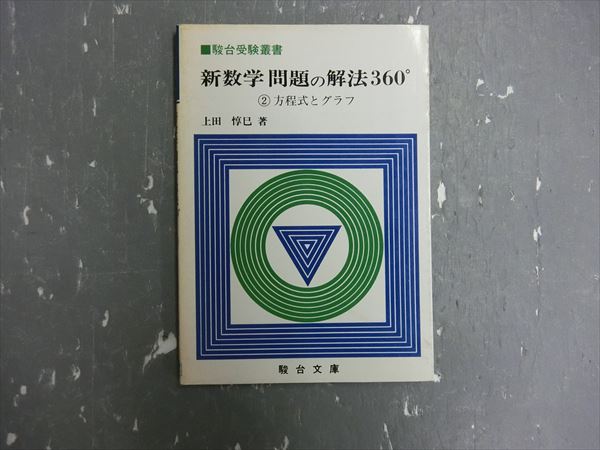

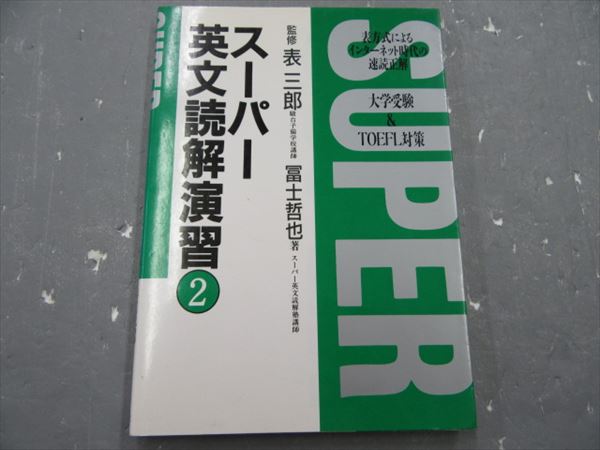

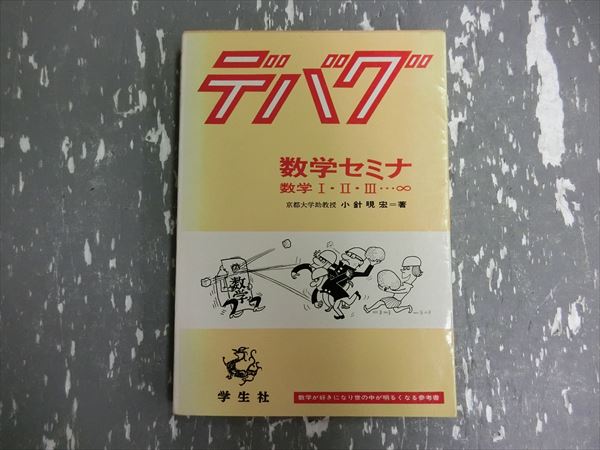
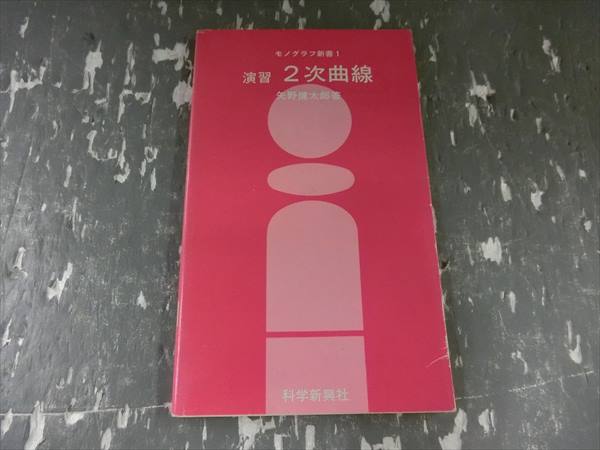
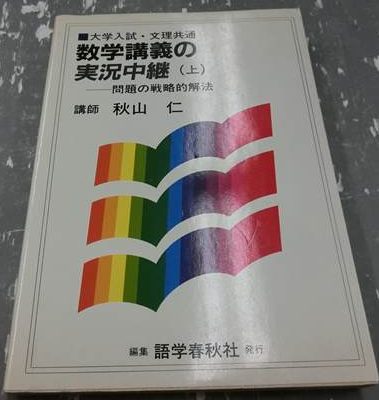

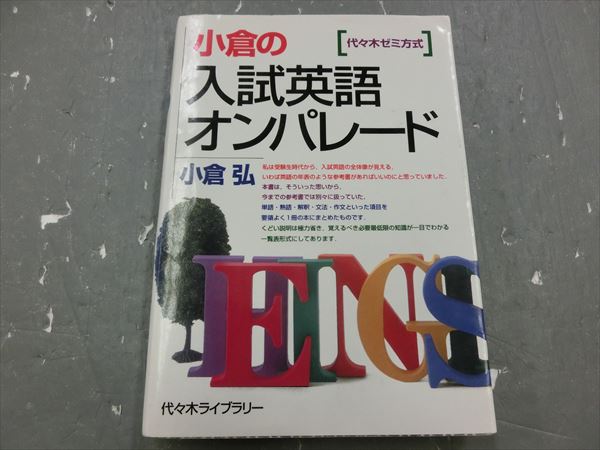
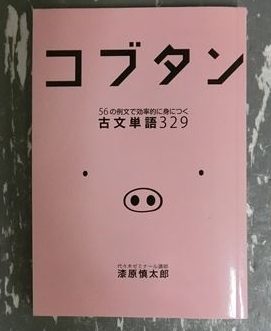

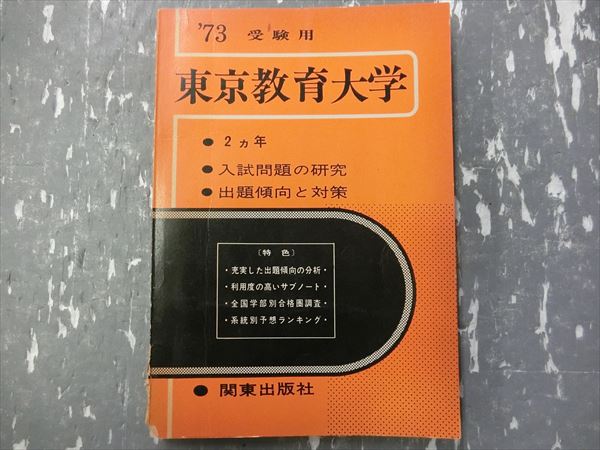
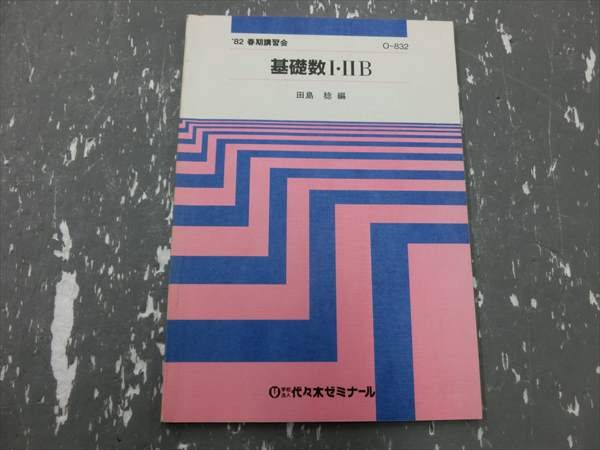


この記事へのコメントはありません。